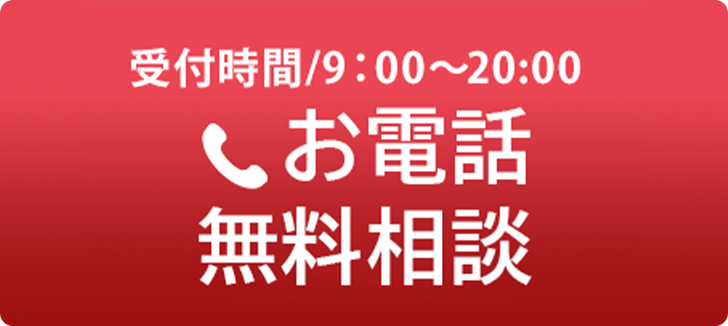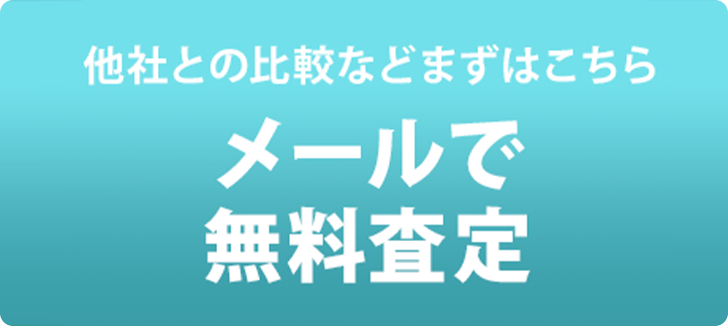事故物件の相続はするべき?相続するメリット・デメリットや相続放棄について解説
2025年7月15日

親や親族が亡くなると、相続手続きを行います。しかし、相続する不動産が事故物件である場合は、相続すべきか慎重に検討しましょう。
事故物件は扱いが難しく、相続によって問題を抱える可能性があります。そのため、事故物件の相続は相続放棄も含めて慎重な判断が必要です。
この記事では、事故物件を相続するメリットとデメリットから相続放棄まで詳しく解説します。適切な選択と注意点を把握するための参考にしてください。
親や親族が亡くなると、相続手続きを行います。しかし、相続する不動産が事故物件である場合は、相続すべきか慎重に検討しましょう。
事故物件は扱いが難しく、相続によって問題を抱える可能性があります。そのため、事故物件の相続は相続放棄も含めて慎重な判断が必要です。
この記事では、事故物件を相続するメリットとデメリットから相続放棄まで詳しく解説します。適切な選択と注意点を把握するための参考にしてください。
事故物件の相続とは

不動産取引では、取引対象の不動産の構造や設備には問題がないものの嫌悪すべき歴史的背景がある場合に、心理的瑕疵があると見なされます。
このような心理的瑕疵を有する物件は、一般的に事故物件と呼ばれます。特に住宅用不動産においては過去に人が死亡した経緯がある物件が該当することが多く、自殺・殺人・孤独死などの不審死、また重大な事故による死亡などが代表的な例です。
また、転倒や窒息のように日常生活で起こりえる事故死、老衰や病死を含む自然死が発生するケースもあるでしょう。このような事案でも、少なからず抵抗感を与える恐れがあります。
心理的瑕疵があると、買い主や借り主にとって契約を締結するかどうかの判断に重大な影響を及ぼす可能性があり、通常の不動産とは区別されるのが一般的です。
事故物件を相続するメリット

相続する不動産が事故物件でも落胆する必要はありません。通常の不動産と比べて扱いが難しいものの、メリットが得られる可能性があります。
事故物件の相続にはどのような利点があるのか、2つのメリットを取り上げます。ご自身にとってメリットがあるかどうか、検討してみてください。
高い需要を見込める場合がある
事故物件と聞くとネガティブな印象を受けやすいものの、事故物件となった要因や不動産の状態によっては買い主が抵抗感を覚えにくいケースもあります。
例えば、室内での自殺から数年が経過している場合や、孤独死が早期に発見されご遺体による汚損が軽度である場合などが挙げられます。
また築浅で設備がよく、駅に近いなど条件のよい物件であれば、事故物件でも高い需要を見込める可能性があるでしょう。
不動産には本来持っている価値があるため、すべての事故物件が嫌悪されるわけではありません。売却や賃貸に出せる不動産は、相続するメリットがあります。
土地活用ができる
事件や事故が起こると、建物に対する抵抗感は避けられません。しかし、建物を解体し更地にするとイメージが緩和される可能性が高まります。
更地であれば柔軟に土地活用ができます。駐車場やトランクルームにして運用したり、土地を不動産会社に売却したりするのも有効です。
ただし、更地にすると住宅用地ではなくなるため、住宅用地のために設けられた軽減措置が適用されず、固定資産税が上がります。更地にした場合にかかる固定資産税を事前に確認してから決定するとよいでしょう。
成仏不動産では、専門知識を備えたスタッフが、相続や売却に関する複雑なご相談にも丁寧に対応しています。
自殺や孤独死、殺人といった背景のある物件から、手がつけられなくなったゴミ屋敷まで、幅広いケースに向き合ってきました。
扱い方がわからず手をつけられずにいる物件についても、状況に合わせて解決の道筋を一緒に考えていきます。
どこから始めればよいか迷っている方は、まず無料相談をご利用いただき、お悩みや疑問をお聞かせください。
事故物件を相続するデメリット

故人が大切にしてきたものを相続するのは価値のあることです。しかし、事故物件を安易に相続すると不要な問題を抱えることになるかもしれません。
ここからは事故物件の相続に伴う3つのデメリットを取り上げます。相続する前にメリットとデメリットを比較し、十分に検討してから決定しましょう。
事故物件には告知義務がある
不動産取引では売り主や不動産会社が買い主や借り主に対し、物件の瑕疵や重要事項を契約前に知らせる告知義務があります。
事故物件は心理的瑕疵がある状態のため、自然死や不慮の事故など事故物件に該当しないケースを除いては、以下の点を告知するとよいでしょう。
・事案の発生時期
・事案の発生場所
・死因
・特殊清掃実施の有無
相続後に賃貸として扱う場合には、告知義務があるのは事案発生もしくは発覚から約3年です。一方、売却する場合には無期限で告知が必要です。
宅地建物取引業法第47条では、売買や賃貸の契約締結の際に申し込みの撤回や解除を妨げるために、故意に事実を告げないことが禁じられています。
事実を隠して告知義務を怠った場合は、法律違反となります。民法第415条に基づき、買い主や借り主は債務不履行による損害賠償請求が可能です。
さらに、状況によっては契約解除を求められる恐れもあります。事故物件の相続により、重大な責任を負うことを頭に入れておきましょう。
買い手が見つかりにくい

事故物件はマイナスイメージが付きやすいため、相続した事故物件を売却や賃貸に出す際には、特殊清掃や大規模なリフォームが必要になる場合があります。
しかし、特殊清掃やリフォームを行ったからといって買い手が見つかるとは限りません。事故物件に対する抵抗感や嫌悪感の程度には個人差があるためです。
仲介で売却する場合は買い手が見つかるまで売却ができず、長い期間を無駄にする恐れがあります。相続したらすぐに売却できると安易に考えている場合は、再考が必要です。
相続税が発生する
事故物件であっても周囲と比べて利用価値が著しく低下していると認められない限り、通常の不動産と同額の相続税が発生する点にも注意が必要です。
不動産は建物と宅地に分けて評価されます。宅地の評価には路線価方式と倍率方式があり、以下の計算式で求めます。
・路線価方式の評価額=1平方mあたりの路線価×奥行価格補正率×面積
・倍率方式の評価額=固定資産税評価額×倍率
建物の評価額は、原則として固定資産税評価額がそのまま用いられます。課される相続税は地域や状況で異なるため、事前によく確認しておきましょう。
申告の有無を確認するには、まず相続税が課される財産の価額の合計額から、控除できる債務と葬式費用の合計を差し引いた金額を計算します。
その金額が遺産に係る基礎控除額を超える場合に申告が必要です。被相続人が亡くなった日の翌日から10ヶ月目の日までに、申告書を提出する必要があります。
提出期限に遅れて申告と納税をした場合には、原則として加算税および延滞税がかかります。相続によって、かえって大きな経済的負担を抱える可能性もあるでしょう。
事故物件相続後の選択肢

故人から遺された事故物件を相続したいと考えている場合、相続後にその物件をどのように扱うかを前もって考慮しておくことも大切です。
相続後には次の3つの選択肢から、自分に合った方法を選ぶことができます。相続予定の事故物件に対し、自分に適切な対応を選ぶことが求められます。
相続人が住む
相続した事故物件を活用するシンプルな方法は、相続人自身が住むことです。事故物件であることが気にならないのであれば、決定しやすいでしょう。
相続人自身が住むことで、手続きの手間や費用を抑えることができます。特にすでに住んでいる場合や住む予定がある場合には、住むのが現実的です。
建物の状態が気になる方には、リフォームや建て替えの検討もおすすめです。住むことで、受け継いだ不動産を維持・管理し続けることにもつながります。
賃貸に出す
ほかに住んでいる家があり、今後も住む予定がないものの不動産を持ち続けたい場合は、賃貸に出すこともできるでしょう。
賃貸のよいところは、定期的な家賃収入が得られる点です。固定資産税を含め、相続でかかるコストをカバーできる可能性があります。
死亡事案発生から期間が空いていたりリフォームされていたりすれば、ネガティブなイメージが軽減される場合もあります。賃料を相場よりも下げることで、借り手が見つかりやすくなるでしょう。
売却する
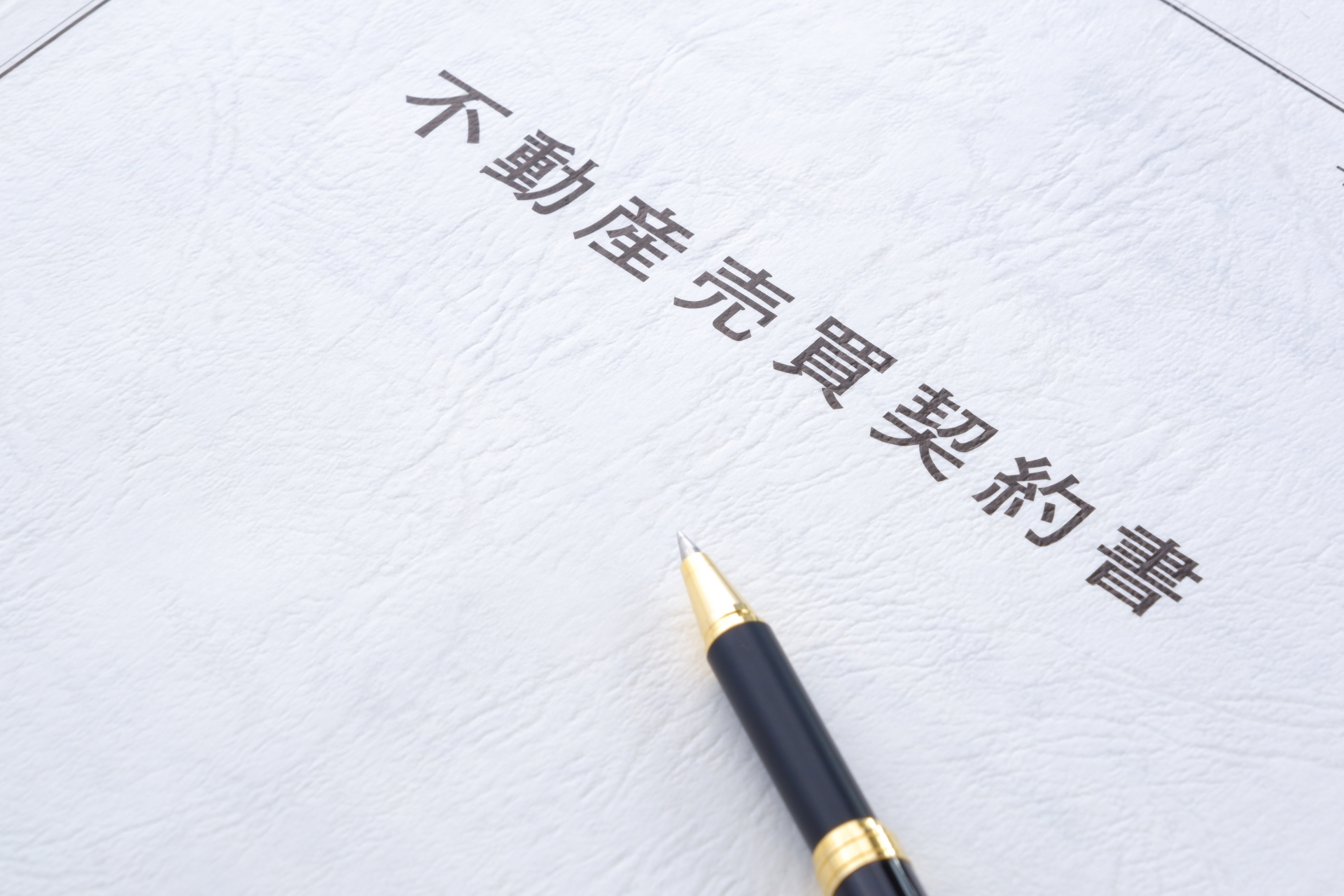
相続人自身での活用が難しい状況なら、相続後に売却して手放す選択肢もあります。売却することで、まとまった資金を得ることができる可能性があります。
買い手が見つかりにくい可能性はあるものの、リフォームでイメージアップしたり、更地にして土地で売ったりすれば売却できる可能性は高まります。
売却方法には、不動産会社を通じて買い主を探す仲介と、不動産会社が直接買い取る買取の2つがあります。どちらの方法を選ぶにしても、事故物件を専門に扱う不動産会社に相談するのが適切です。
成仏不動産は、事故物件を専門に扱う不動産サービスとして、豊富な知識と経験をもとに相場を丁寧に調査し、不動産本来の価値を見きわめた上での高額買取に力を入れています。
過去に査定で値がつかなかった物件であっても、状態を正しく評価し、買取につなげた事例も多くあります。
仲介や賃貸では難しいとされる物件についても前向きに検討しており、荷物や家具が残っている場合でも対応可能です。
現在の状況に迷いがある方は、無料相談をご利用いただき、お考えをお聞かせください。
事故物件を不動産会社へ売却するメリット・デメリット

相続した事故物件に住む予定がなく、賃貸に出しても借り主が見つかりにくそうな物件なら、不動産会社に直接売却することも検討してみましょう。
扱いにくい事故物件を所有し続けるよりも、売却して手放すことで負担を軽減できるでしょう。売却による3つのメリットと1つのデメリットをそれぞれ解説します。
メリット①:相続人の費用の負担を減らせる
不動産を相続すると、費用面での負担がかかります。不動産を持っている限り固定資産税がかかるうえに、管理やメンテナンスにも費用が必要です。
不動産会社に売却すれば、所有権が移転するため、以後の維持費用はかかりません。
また、仲介で売却した場合には不動産会社に仲介料を支払わなければなりません。不要な支払いが生まれない点も、不動産買取のメリットです。
物件の状態や立地条件によっては、一定の売却益を得られる可能性もあります。リフォームにお金をかけずに売却できる可能性もあります。
メリット②:相続人の時間の負担を軽減できる

仲介で売却する場合は、買い手が現れるまで待ち続けなくてはなりません。種々の手続きも必要で、売却までに早くても2〜3ヶ月を要します。
それに対し、買取なら不動産会社自身が買い主となるため、売買契約が締結されれば、すぐに不動産を手放すことができます。スピーディーな現金化も可能です。
購入希望者の内覧への対応や交渉の手間も省けます。自由なスケジュールで物件の引き渡しができるため、自分の都合に合わせやすいのも利点です。
メリット③:売却後の責任を免除できる場合がある
売り主が売却時に告知義務を果たしていれば、売却後に物件自体に欠陥が見つかった場合でも基本的に契約不適合責任は免除されます。
契約不適合責任とは、売り主が引き渡した商品が契約内容と異なる場合に、買い主に対して一定期間負う責任のことです。
買い主となる不動産会社は不動産の専門家です。事前に査定をしたうえで買取を行っているため、大半は責任を免除する契約条件になっているでしょう。
デメリット:売却価格が安くなる

事故物件は、一般物件よりも売却相場価格が下がる傾向にあります。死亡事案の内容ごとに異なり、一般価格との違いは以下のとおりです。
・自然死や事故死:一般価格の10~20%ほど下がる
・自殺:一般価格の20~30%ほど下がる
・他殺:一般価格の30~50%ほど下がる
さらに不動産会社に売却する場合は、仲介で売却するよりも価格が下がる恐れがあります。これはリフォームや修繕費用が差し引かれるためです。
物件の状態や不動産会社によって変動はあるものの、仲介による売却価格の6〜8割程度にとどまる可能性があります。
多少売却価格が安くなったとしても売却したいなら、事故物件の買取経験が豊富な不動産会社を頼りましょう。相続や税金の相談もできる不動産会社を選ぶのがおすすめです。
成仏不動産は、2019年のサービス開始以来、2025年6月時点で6,200件を超えるご相談を受けてきた事故物件買取の専門サービスです。
相続手続きや特殊清掃、遺品整理に加え、お祓いやご供養といった心情面のケアまで含めて、買取に関わるさまざまな課題にワンストップで対応しています。
事故物件を引き継ぐことに迷いがある方や売却に踏み切れず悩んでいる方は、まず無料相談をご利用いただき、今の状況や気がかりな点をお聞かせください。
相続診断士の資格を持つスタッフが、一つひとつ丁寧に向き合いながら対応いたします。
事故物件を売却するときの注意点

事故物件の売却は単純なものではありません。十分な検討をせずに売却すると、後悔する結果を招くおそれがあります。
事故物件を売却する際に、前もって心に留めておくべき3つの注意点を解説します。予期せぬトラブルを防ぐためにも、事前に確認しておきましょう。
コストがかかる
不動産の売却にはさまざまなコストがかかります。土地や建物を売るために直接かかる譲渡費用には、以下のものが含まれます。
・仲介手数料
・印紙税
・建物の解体費用および解体による損失額
また、土地や建物を売ったときに課される譲渡所得税の納税も必要です。以下の計算式で、課税譲渡所得税を割り出します。
・譲渡価額-(取得費+譲渡費用)-特別控除額=課税譲渡所得金額
・課税譲渡所得金額×税率=譲渡所得税額
税率は土地や建物の所有期間によります。5年を超える長期譲渡所得なら所得税と住民税を合わせて20%、5年以下の短期譲渡所得なら39%です。
その他、売却前に売り主自身が手配して特殊清掃やリフォームを行う場合には、その費用も負担する必要があります。詳しくは国税庁のホームページをご覧ください。
売却で得られる利益は少ない

前述のとおり、事故物件の売却価格は一般的な物件に比べて大きく下がる傾向があります。不動産会社によってはほとんど価格が付かない可能性もあるでしょう。
また、売却益が出ても売却にかかるコストが高ければ、実際に手元に残る金額は少なくなります。高額での売却が見込めない状態であれば、売却のタイミングや方法については慎重に検討することが大切です。
成仏不動産では、司法書士や税理士と連携しながら、法的な手続きや税金に関するご相談にも対応できる体制を整えています。
相続にまつわる実務や判断が複雑になりがちな場面でも、多方面から支援できる点が大きな強みです。
また、在籍するスタッフ全員が相続診断士の資格を取得しており、円滑な手続きが進められるよう丁寧にお手伝いしています。
専門知識がなくても心配は不要です。すでに事故物件を相続した方や、これから相続する可能性がある方も、まずは一度ご相談いただき、今の状況をお聞かせください。
事故物件の相続放棄

事故物件の相続により不利益を被る恐れがある場合、相続をせずに、被相続人の権利義務をすべて放棄するという選択肢もあります。
ただし、すべてのケースで相続放棄が賢明な判断になるとは限りません。相続放棄をおすすめするケースとおすすめできないケースをそれぞれ取り上げます。
相続放棄をおすすめするケース
そもそも相続は、被相続人の遺産のすべてを引き継ぎます。プラスの財産である資産とマイナスの財産である負債の両方を、ともに相続しなければなりません。
被相続人の資産が少なかったり事故物件以外にも負債を抱えていたりするケースでは、相続放棄することで財産を得ない代わりに債務も負わない決定ができます。
また事故物件を売却や賃貸で出せないと、空き家を抱えるリスクもあります。収入が入らなければ、維持費用や固定資産税で支出ばかりが増えてしまうでしょう。
さらに、相続に関する親族間の話し合いにはトラブルが付き物です。遺産が少なく分散させるのが難しいと、話し合いに手間取る可能性があります。
このように、相続によって金銭的・精神的な不利益が明らかな場合には、相続放棄する方が負担が少なくて済みます。
相続放棄をおすすめしないケース

被相続人の負債よりも資産が多い場合は、相続放棄は避けた方がよいでしょう。相続放棄後に隠れた財産が見つかることもあるため、正確な把握が大切です。
また、事故物件ではあっても状態や立地がよく売却や賃貸に出せる見込みがあるなら、相続する方が将来的にプラスになるはずです。
相続放棄をすれば、その権利は次順位の相続人に移ります。ほかの相続人が負担を抱えきれない状態にもかかわらず、事前の相談もなく相続放棄をするとトラブルの原因となるため、性急に相続放棄を決めるのは避けましょう。
相続放棄の手続き

遺産相続は、故人の財産を有効に活用し、その後のトラブルを防ぐことを目的とした法的な制度です。そのため、相続放棄にも法的な手続きが必要です。
自分で手続きを行うこともできますが、流れを理解していないと正しく相続放棄ができない可能性があります。大きく5つのステップに分けて順に解説します。
相続放棄の費用を準備する
1つ目のステップは、相続放棄にかかる費用の準備です。以下の費用をあらかじめ準備しておけば、手続きの際に手間取ることを防げます。
・収入印紙
・郵便切手代
・戸籍謄本取得に必要な代金
収入印紙は全国一律で800円分です。郵便切手代は地域や手続きの方法によって異なるため、申し立てする地域の家庭裁判所の情報を確認しましょう。
これらの費用を申述人自身が準備すれば、費用は数千円程度に抑えられます。ただし、ご自身での手続きが不安な方は、数万円で司法書士に依頼することも可能です。
相続放棄に必要な書類を用意する

2つ目のステップは、相続放棄に必要な書類の用意です。申述人の立場によって必要な書類の種類が異なるため、間違いのないようにしましょう。
すべての申述人に提出が求められるのは、相続放棄申述書です。家庭裁判所に置かれている用紙を用いるか、裁判所のホームページからダウンロードできます。
申述書には本籍や住所、氏名や相続放棄の理由など必要事項の記入と捺印をします。記入に不備があると相続放棄が受理されない可能性があるため、慎重に記入しましょう。
また、添付書類として申述人の戸籍謄本の原本かコピーが必要です。加えて、申述人の相続順位によって具体的に必要な戸籍謄本が異なります。
さらに債権者や市町村役場からの通知書をはじめ、相続の開始を知った日がわかる書類があれば、その書類のコピーも用意しておきます。
書類の種類によっては、取得までに時間がかかることもあります。なるべく早めに用意して、不備のないようにしてください。
家庭裁判所に相続放棄を申し立てる
3つ目のステップは、家庭裁判所に対する相続放棄の申し立てです。申述書と必要書類を、被相続者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に提出します。
相続放棄の申し立ては、相続人本人が行うのが原則です。相続人が未成年であれば、法定代理人として親権者が申し立てる必要があります。
申し立てを行う家庭裁判所が遠方にあり直接提出が難しい場合は、郵送で手続きが可能です。手続きに必要な条件がご自身に当てはまるかどうか、事前に管轄の家庭裁判所や自治体に確認しておきましょう。
相続放棄申立後に照会書が届く

4つ目のステップは、照会書の受け取りと返信です。申し立てから7〜10日程度で、家庭裁判所から相続放棄に関する照会書が送付されることがあります。
照会書とは、相続放棄の申述が相続人本人の真意かどうかを確認するための書類です。すべてのケースではありませんが、届いたら同封されている回答書に記入しましょう。
照会書には被相続人の死亡日と死亡を知った日、被相続人との関係、申述した理由などに対する質問が記載されています。
この回答次第で、相続放棄が認められるかが決定されます。不備がある場合や記入内容に問題がある場合は、不受理になるかもしれません。
申述書の記載内容と矛盾しないよう、質問文をよく確認したうえで正確に回答しましょう。
合わせて、必要書類の追完を求められることもあります。できるだけ速やかに対応し、返信の遅れを避けるよう心がけましょう。
相続放棄が許可されたら相続放棄申述受理通知書が届く

相続放棄が許可された場合の5つ目のステップは、相続放棄申述受理通知書の受け取りです。この書類が届いた日から、相続放棄が法的な効力を持ちます。
照会書に対する回答を返信してから、7〜10日程度で届くでしょう。照会書による確認が必要ない方の場合は、申し立てから1〜2週間程度で届きます。
相続放棄申述受理通知書は、万が一紛失しても再発行できません。受け取ったら必ず大切に保管してください。
相続放棄の手続きはこれで完了ですが、後日のトラブルや責任の誤認を防ぐためにも、債権者への連絡を行うことをおすすめします。
相続放棄を知らせる際には、申述が正式に受理されたことを証明する相続放棄申述受理証明書を求められるケースがあります。
相続放棄申述受理証明書は家庭裁判所に申請書と身分証明書のコピー、利害関係疎明資料のコピーを郵送すれば発行可能です。
なお、家庭裁判所が相続放棄を認めない場合には、申し立てた相続人本人宛に相続放棄不受理通知書が届きます。
内容に納得できないなら、受け取りの翌日から2週間以内に高等裁判所に即時抗告を申し立てましょう。ただし、即時抗告しても認められない恐れがあります。
申述書の記入や必要書類に不備があったために受理されないとすれば、時間を無駄にしてしまいます。少しでも不安がある方は、専門家に助けを求めましょう。
成仏不動産では相続診断士の資格を持つスタッフに加え、司法書士・税理士・専任の弁護士と連携しながら、それぞれの分野に対応できる体制を整えています。
個別に専門家へ依頼すると時間や費用がかさみがちですが、成仏不動産なら一か所で手続きをまとめて進められるため、手間をかけずに事故物件の売却から相続放棄まで対応できます。
対応エリアは関東を中心に全国に広がっており、遠方に相続予定の物件がある場合でもご相談可能です。手続きに迷っている方は、まず無料相談をご利用いただき、状況やお悩みをお聞かせください。
相続放棄の注意点

相続は相続人に与えられる権利ですが、義務でもあります。相続するのが事故物件だから放棄したいと思っても、自由に放棄できるわけではありません。
相続放棄を検討している方が把握しておくべき4つの注意点をご紹介します。
本当に相続放棄が適切な選択かどうか、慎重に検討しましょう。
相続財産を使ってしまうと相続放棄が認められなくなる
相続放棄の手続きが完了する前に相続財産を使用すると、申述書を提出していても相続放棄が却下される恐れがあります。
根拠は民法第921条です。相続人が相続財産の全部または一部を使用したときや処分したときは、相続を単純承認したと見なされることが定められています。
具体的には、事故物件の遺品整理をして家財を処分するほか、事故物件に残っていた現金を使ったり家財を売って現金化したりした場合が該当します。
相続財産を使うか処分する行為は、相続人にのみ認められている行為です。これらを行うと相続人の権利を行使したことになり、相続の意思があると判断されます。
家財の価値には明確な基準がないため、財産的に価値がない家財でも専門家に意見を仰いでから扱うようにしましょう。
期限を過ぎると相続放棄できない

相続放棄の申述書の提出を含め相続に関する決定は、民法第915条により相続の発生を知ってから3ヶ月以内に行うよう義務づけられています。
期間に制限が設けられているのは、相続人の権利関係を早期に安定させることにより、相続の遅延や混乱を避けるためです。
この期間は熟慮期間と呼ばれており、相続するかどうかを判断するための猶予です。3ヶ月を過ぎてから相続放棄の申し立てをした場合は、原則として受理されません。
ただし、期間中に相続財産の状況を調査したうえでも相続放棄するかどうかを決められない場合には、家庭裁判所への申し立てで期間を伸長できます。
ご自身のためにもほかの相続人のためにも、早急に決定するのがおすすめです。とはいえ、何らかの事情で期間が過ぎてしまったら弁護士に相談してみましょう。
相続開始後にしか相続放棄できない
将来的に相続する財産に事故物件が含まれていると分かっていても、被相続人の生前には相続放棄はできません。
生前の相続放棄が可能になると、ほかの推定相続人から相続放棄を強制される恐れがあり、トラブルの原因になりえるためです。
また、被相続人が生きているうちの財産調査には限りがあります。隠れた資産があっても明確にならず、放棄を確定する十分な判断材料が揃いません。
このような理由から、相続放棄ができるのは被相続人が亡くなってからとなります。しかし、前もって相続後の身の振り方を検討しておくのはよいでしょう。
相続財産清算人がいない場合は放棄しても財産の管理義務が残る

相続財産清算人とは、戸籍上相続人がいない場合やすべての相続人が相続放棄した場合に、相続財産の管理や清算を行うために家庭裁判所が選任する人です。
利害関係人が家庭裁判所に申し立て、家庭裁判所が選任します。自分が相続放棄することで相続人がいなくなる場合には、相続人本人が申し立てを行うことも可能です。
申し立てをしても権限が認められない場合や、予納金の納付がなされていない場合は、相続財産清算人が選任されない可能性があります。
相続財産清算人がいない状況では財産の管理や清算をする人がいないため、相続放棄をした人に管理義務を果たす責任が残ります。
相続放棄をすればすべての責任から直ちに解放されると考え、安易に決断しないよう注意が必要です。
事故物件の相続にお困りなら

この記事では、事故物件を相続した場合に売却するメリットやデメリット、相続放棄をする場合の手続きや注意点をまとめて解説しました。
相続するのが事故物件だとわかっているなら、相続前にその不動産をどう扱うかを検討できます。ご自身にとってよりよい選択をしましょう。
通常の物件を相続するケースとは状況が異なります。後悔しない決定をするためには、事故物件の相続や売却の専門知識がある相談先を見つけることが大切です。
成仏不動産は、事故物件を専門に扱うサービスとして、豊富なノウハウを有しています。全国どこからでもご相談いただける体制が整っており、物件の状況を問わず幅広く対応可能です。
相続放棄・売却の判断・遺品整理・税務に関する不安など、事故物件にまつわるあらゆる悩みに寄り添いながら、専門家とともに解決に向けて具体的な道筋をご提案しています。
相談や査定は無料で受け付けていますので、自分だけで結論を出す前に、まずは成仏不動産にご相談ください。