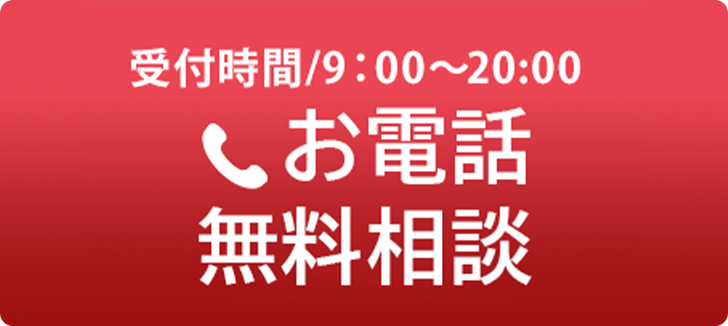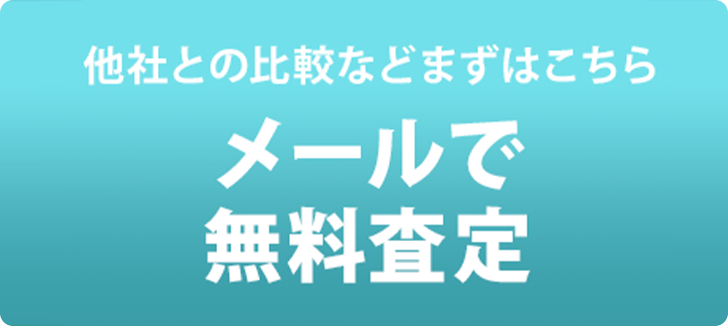賃貸物件が事故物件になってしまった場合の対処法|告知義務や損害賠償のリスクも解説
2025年9月19日

賃貸物件を所有や管理している方のなかには、入居者が室内で亡くなった場合の対処にお困りの方もいるのではないでしょうか?
管理している賃貸物件で入居者が亡くなり、突然の事態に動揺して適切な対処がわからず戸惑う方も少なくありません。
しかし、正しい情報開示と空室対策を行えば、再び物件を貸し出すことができます。
本記事では事故物件とは何かという基本から、告知義務や損害賠償のリスクまで、法律と実務の両面から対処方法をわかりやすく解説します。
また、心理的負担への軽減になれば幸いです。冷静に適切な判断をしましょう。
事故物件とは
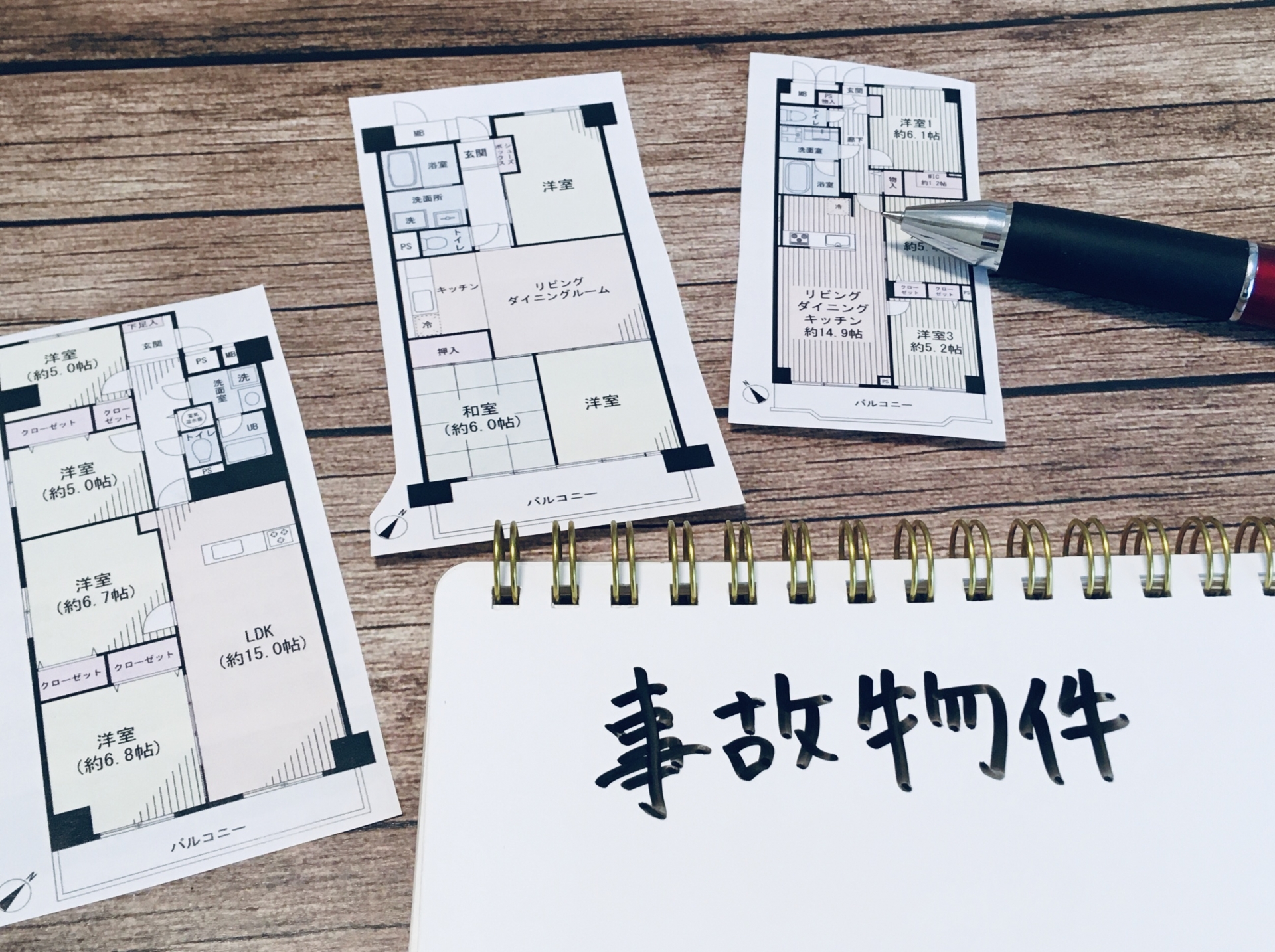
国土交通省は、2021年10月に不動産取引における人の死の告知に関するガイドラインをまとめました。主な対象とする範囲は居住用の不動産を取り扱っています。
事故物件とは、過去にその物件で人が亡くなる出来事があり、一般的に心理的な抵抗感を抱かれるような賃貸物件を指します。
具体例としては自殺・他殺・孤独死で発見が遅れ、特殊清掃が必要になったケースや、火災による死亡事故などが挙げられるでしょう。
ガイドラインでは、自然死や一般的な日常生活での不慮の事故は原則として賃貸借契約では告知義務がなく、事故物件の定義から外れることが少なくありません。
留意すべき点として、死亡に関する事案はガイドラインに当てはめるだけでなく、個別の状況を踏まえて慎重な判断が大切です。
賃貸物件が事故物件になりうる例

賃貸物件が事故物件とされるのは、主に死亡事案が発生した場合です。
ほかに事件性や認知度の高いケース、社会的な影響が大きい事案は事故物件としてあげられる場合が少なくありません。
入居者が自死した
賃貸物件で入居者が自死した場合、その物件は宅地建物取引業者が定めたガイドラインでは心理的瑕疵物件と判断され、事故物件として扱われます。
貸主には次の入居者希望者に対して死亡事案を告知する義務が生じます。
一般的に告知義務の目安は発生からおおむね3年間とされていますが、3年を超えても心理的瑕疵が残ると判断され、告知が求められることも少なくありません。
実際に厚生労働省の2023年度のデータによると、自殺者のうち13,414人が自宅で命を絶っており、自宅での自死は決してまれではありません。
部屋で事件が起こり人が亡くなった
賃貸物件で殺人事件などの重大な事件が発生した場合、事故物件は心理的瑕疵のなかでも特に重いケースとされます。
殺人事件は単なる物件内での出来事にとどまらず、周辺地域の住民にも不安や不信感を与えるなど、社会的な影響が大きいのが特徴です。
さらに事件がテレビなどで報道されると広く拡散され、建物全体のイメージに深刻なダメージを与える可能性があります。
過去の裁判例からみても建物の有無に関わらず、一般的なガイドラインのおおよそ3年の告知義務にはとどまらず、長期にわたって説明が必要になります。
火災により人が亡くなった
火災によって人が亡くなった場合、その物件は事故物件として扱われます。国土交通省のガイドラインでも、心理的瑕疵に該当するとされ、次の入居者に対して死亡事故を告知する義務があります。
実は火災によって人が亡くならなかった場合でも、火事が発生した事実だけで建物に大きな損傷がある場合には、心理的瑕疵となるため告知が必要になるケースも少なくありません。
火災事故は物件の印象を大きく下げ、賃料の値下げや空室期間の長期化につながる可能性があります。
長期間発見されない孤独死があった

事件性がなく死因が老衰や持病などの自然死でも、死後3日以内に発見され異常がなければ告知義務が発生しないケースがあります。
一方、孤独死で長期間発見されないと事故物件となり、特殊清掃や大規模なリフォームが必要になります。
季節や気温にもよりますが、亡くなってから3日ほどで腐敗が始まり、腐敗臭や体液が床や壁紙に染み込んでいくのが一般的です。
通常の清掃では対応できないため、専用の薬剤や機材を使った特殊清掃が必要になるでしょう。
成仏不動産では、事故物件の専門家として、オーナーのお悩みに丁寧に対応してきた実績があります。
貸主の負担が少しでも軽くできるよう、事故物件に特殊清掃とご供養を行い、心が安らぐ成仏物件となるまでしっかりサポートします。
成仏不動産は事故物件に付加価値を加え、イメージを高める施工を心がけ、嫌われる物件から選ばれる物件へと生まれ変わらせるのが私たちの使命です。
事故物件に関するお悩みがある方は、無料相談をご活用ください。
賃貸物件で人が倒れている場合や亡くなっている場合の対処法

貸主は、借主の許可なく部屋に入ることが原則として禁止されています。
たとえ遠くに住む親族から「連絡が取れないので部屋を確認してほしい」と頼まれても、借主の許可なく無断で部屋に入ると、法律上住居侵入罪に問われる可能性があるので注意しましょう。
貸主が正当な理由により賃貸物件に立ち入った際、もし室内で人が倒れていた場合やすでに亡くなっていた場合は、冷静な初動対応がたいへん重要です。
間違った対応をしてしまうと、後々の手続きや関係者とのやりとりに影響を及ぼしかねません。
非常時に備えて、連絡先と行動手順を把握しておくことが、落ち着いた初動対応につながります。
救急や警察に連絡をする
入室して人が倒れていた場合は、まず落ち着いて意識や呼吸があるかを確認しましょう。意識や呼吸の有無によって、連絡先が異なります。
意識があると判断できた場合はすぐに救急の119番へ連絡しましょう。しかし、すでに亡くなっている可能性がある場合は警察の110番への通報が重要です。
現場の状況によっては、倒れている人の息はあるが事件性がありそうな場合、救急にも警察にも連絡するのかと迷う際は救急のみの通報で問題ありません。
万が一、搬送先で人が亡くなると自動的に警察にも連絡がいきます。まずは、人命救助を優先しましょう。
入居者の親族や保証人に連絡をする
賃貸物件で借主が亡くなっていた場合や、救急搬送された後に死亡が確認された場合は警察による現場検証が行われ、死因に事件性がないか確認されます。
警察からの連絡をうけた後、賃貸契約書に記載された親族や保証人に入居者が亡くなったことを速やかに伝えましょう。その際に伝える内容は以下のとおりです。
・死亡の事実
・未払いの家賃
・原状回復の内容と費用
・遺品整理
・今後の対応
賃貸借契約は借主が亡くなっても自動的に契約が終了するわけではなく、原則的には家賃が発生し続けるため、解約するにはあらためて手続きが必要です。
家賃が自動引き落としの場合、借主の死亡に伴い銀行口座が凍結されるため、速やかに保証人との話し合いをしましょう。
管理会社に連絡をする
賃貸管理を管理会社に委託している場合は、借主の死亡が判明した時点で速やかに管理会社へ連絡する必要があります。
借主が亡くなった際の対応は、管理会社が行うことになります。伝える内容は以下のとおりです。
・入居者の氏名と部屋番号
・発見日時
・発見状況
・事実確認
今後の対応の流れを、オーナーが事前に把握しておくことが重要です。
対応の手順や連絡体制、必要な書類などを確認しておくことで、いざというときにも冷静に対処できます。
トラブルを防ぐためにも、管理会社と日頃からしっかりと連携をとり、情報共有しておきましょう。
賃貸物件で人が倒れている場合や亡くなっている場合の注意点

前述のとおり、室内で倒れている方や亡くなった方を発見した場合は、まず警察への通報がとても大切です。適切な対応を怠ることは損害賠償責任や刑事責任を問われる可能性があります。
警察は、死因に事件性や事故の可能性があるのかどうかを判断するために、現場検証を行います。主に行う活動は以下のとおりです。
・ご遺体の確認:事件性の有無
・生活状況と亡くなった場所の確認:死因の判断するため
・病歴や収入と生命保険の加入状況の確認
・外見的な状況から解剖の可能性もあり
上記の活動からもわかるように、現場の状況はとても重要な判断材料になるため、発見者としていくつかの注意点に気を付けましょう。
倒れている人や遺体に触れない
賃貸物件で生存確認の目的で入室し、倒れている人や遺体を発見した場合は正当な理由がない限り、その方に触れることは避けなければいけません。
むやみに遺体に触れたり動かしたりすると、状況によっては刑法190条の死体遺棄罪や死体損壊罪に問われる可能性があります。
そのため、警察が到着するまでは現場の状況をなるべくそのまま保ち、安易に手を触れないように注意しましょう。
ただし、すべてのケースで触れることが違法になるわけではありません。入室時にまだ息がある状態で、救命措置などを行うために触れた場合は正当な行為として認められます。
また、現場で倒れている人や遺体の写真を撮影したり、情報を広めたりする行為は控えてください。プライバシーの侵害やトラブルの原因になる可能性があります。
部屋の中のものに触れたり移動させたりしない
事件や事故の可能性がある場合は、警察が到着するまで現場をそのまま保つ義務があります。ときには、証拠隠滅や妨害になる行為として刑法104条に問われる可能性もあります。
警察や救急に通報した際は到着するまでは部屋の中のものに触れたり移動させたりせず、発見者として可能な限り、情報提供に協力しましょう。
現場の状況を保つためだけでなく、法律上や衛生面でも問題がある場合があるため、たとえ臭いが強くても窓を開けるのは控えましょう。
成仏不動産では事故物件の不動産に特化し、葬儀社や司法書士、行政機関と連携しながら死後の不動産整理を事業の中核にしています。
お持ちの物件が事故物件になり、扱いが難しい不動産を相談診断士の資格を持つ営業担当が、オーナーの悩みに寄り添いサポートします。
事故物件の取扱いには普段の不動産取引よりも多くの配慮や手順が必要なため、不安を感じている方は、まず無料相談をご利用ください。
賃貸物件が事故物件になってしまった場合の対処法

「事故物件になってしまったら、まず何をすればよいのか?」と不安に感じるオーナーの方も少なくありません。
まずは事故物件の取扱いに詳しい専門業者への相談が重要です。状況や物件の状態に応じて、特殊清掃やリフォームの依頼など適切な対応策を提案してもらえるため、冷静に対処することができます。
不安や悩みを一人で抱え込まず、信頼できる専門家の力を借りることで、オーナーとして適切な判断と行動がしやすくなります。
特殊清掃を依頼する
事故物件に該当する物件はほとんどのケースで遺体が関わっています。遺体の発見現場は死臭といわれる強烈な腐敗臭が発生し、体液や血液など汚れも特殊です。
一般的なハウスクリーニング業者では、特殊な臭いや汚れの清掃には対応していないことが多く、作業を断られる場合も少なくありません。
こうした清掃を自力で行っても、臭いや汚れの性質が特殊なため、一般の方では対応が難しいのが現実です。
加えて人が亡くなった事実がある現場に入ること自体、精神的に大きな負担を伴うこともあります。
事故物件の特殊清掃では、見た目だけをきれいにする表面的な清掃では不十分です。状況によっては、体液などが床や壁の内部にまで染み込み、建材が深く傷んでいることもあります。
専門の知識を持つ業者が現場を調査し、元の状態に戻すための対応を判断したうえで、専用の薬剤と機材を使って汚れと臭いを徹底的に除去します。
遺品整理を依頼する

遺品整理は原則、親族や相続人、連帯保証人が行います。相続人が相続放棄を申し出た場合は、遺品整理を行えない場合が少なくありません。
故人に身寄りのない場合は故人が亡くなった住所地の自治体に連絡をし、遺体の引き取りや火葬と埋葬を進めることができますが、遺品整理は行いません。
部屋に残された遺品や残留物の整理や処分は、結局はオーナーの対応になるケースがほとんどです。本来、遺品整理の費用はオーナーが負担する義務はありません。
しかし、遺品整理が行われないままでは部屋を片付けることができず、新たな入居者を迎えることもできません。やむを得ずオーナーが費用を負担して整理を進めるのが現実です。
リフォームを依頼する
特殊清掃を行っても、体液や血液の汚れ、強い臭いが完全には除去できないことが少なくありません。
そうした場合、クロスやフローリングの張り替えの部分的な修繕から、場合によっては全面的なリフォームによって原状回復を行う必要があります。
リフォームを依頼する際は、事故物件であることをリフォーム業者にきちんと伝えることが重要です。経験豊富な業者なら適切な施工だけでなく、アドバイスも望めるでしょう。
フルリフォームによって室内の印象が大きく変わることで、事故物件に対する心理的ハードルが下がり、次の入居者募集がしやすくなる可能性があります。
ただし注意が必要なのは、たとえリフォームをしても事故物件であることの告知義務は引き続き残る点です。
お祓いやご供養を行う
事故物件は心理的瑕疵物件とも呼ばれ、お祓いやご供養を行うことがありますが、お祓いやご供養は法律で義務づけられているものではありません。
近年ではオーナーや管理会社の判断で、入居者への配慮や心理的ケアの一環としてお祓いやご供養を依頼するケースが増えています。
お祓いやご供養の依頼先は、一般的に神社やお寺で、管理会社を通じて手配されることもあります。
お祓いを行うことでオーナー自身や今後の入居者にとって気持ちの整理がつき、安心感につながる精神的な効果が期待できるでしょう。お祓いやご供養はあくまでも、心のケアの一環にすぎません。
成仏不動産では、特殊清掃や遺品整理、リフォームとお祓いまでさまざまなご相談を専門的な知識をもつ相談員がワンストップでサポートします。
事故物件の専門家として知識と経験から貸主のご希望に寄り添い、正しい不動産相場で誠実に評価し高額の買い取りをご提案します。
全国に支店を展開しているため、地域を問わず対応可能です。遠方の事故物件でも安心感をもってご相談いただける体制が整っています。
お気軽に成仏不動産の無料相談をご利用ください。
https://jobutsu.jp/cms/tadashiikaitori/contact/
賃貸物件が事故物件になった際の大家の対応

大家の事故物件発生後の対応は、心身ともに大きな負担となる場合があります。適切な手順を踏むことで、トラブルの拡大を防ぎ、今後の賃貸運営に役立てることができます。
事故物件が発生した際には、物件の契約に関する対応に加えて、法的な手続きや金銭の清算も適切に行うことが不可欠です。
不安な場合は、専門業者や弁護士、司法書士に相談しながら対応を進めましょう。
賃貸契約の解約
入居者が亡くなった場合でも、賃貸契約は自動的に終了するわけではありません。
民法第896条により、入居者の権利義務は原則として法定相続人に承継されるため、契約関係も引き継がれているとみなされます。
よって相続人または連帯保証人と連絡を取り、書面による合意に基づき、賃貸借契約の解約手続きを行う必要があります。
解約手続きを行わない限り、賃料の債務は継続し、未払い家賃が発生する可能性も少なくありません。
退去日や鍵の返却なども、契約上の義務として明確にしておくことが重要です。
敷金の返還
賃貸借契約が終了した後は、敷金の清算を行いましょう。
未払い賃料や原状回復費用、室内清掃費用と修繕費用などを敷金から差し引いて、残額がある場合には相続人または連帯保証人に対して返還手続きを行うことになります。
特殊清掃やリフォームが必要な場合でも、これらの費用を敷金から差し引けるかは、契約内容や損耗の程度によって異なります。
発生した費用の内訳や根拠を明確にし、相続人に対して丁寧に説明を行い、合意をえることが望ましいです。
滞納家賃の請求

入居者が生前に家賃を滞納していた場合、未払賃料債務は、民法第896条に基づき相続人に承継されます。
大家は相続人または連帯保証人に対し、未払い分の家賃の請求ができます。
請求にあたっては内容証明郵便などを用いて、金額・支払期限・支払方法を記載した通知書を送付し、債権の存在を明確にしておくことが重要です。
相続人と連絡が取れない場合や支払が履行されない場合には、弁護士に相談のうえ、民事訴訟や少額訴訟制度の利用を検討しましょう。
損害賠償請求の交渉
入居者の死亡により、室内に著しい損傷や汚損と腐敗などが発生した場合には、原状回復費用を超える損害が生じることがあります。
このような損害は事案の内容や契約書の条項に基づき、相続人または連帯保証人に対して損害賠償請求を行うことが可能です。
ただし、損害の範囲や請求の可否と過失の有無は個別の事情により異なるため請求前に弁護士などの法律専門家に相談し、法的根拠を確認して対応しましょう。
損害賠償請求ができないケースは?

損害賠償請求ができないケースとして、入居者に過失がない孤独死や病死などがあげられます。不慮の事故や自然災害などの不可抗力による死亡も対象です。
また、借主が死亡し相続人全員が相続を放棄した場合は、債務を引き継ぐ者がいないため請求できません。
借主に過失や責任がない場合、経年劣化など原状回復義務の範囲外の損傷、契約書に免責特約がある場合は貸主は損害賠償請求が行えません。
遺族とのトラブルを防ぐためにも、冷静な対応を心がけましょう。
成仏不動産では、相続や賃貸の契約内容に詳しい専門知識をもつ相談員が貸主のご相談に丁寧に対応しております。
事故物件に特化した専門家として、今まで数多くの訳あり物件に向き合ってきた経験を活かし、貸主の今後の意向に添えるサポートをしていきます。
事故物件の扱いに悩んでいる方に向けて、状況に応じた解決策を一緒に考えていきましょう。まずは成仏不動産の無料相談をご利用ください。
新規の入居者への告知義務とは

住居物件で過去に物件内で人が死亡した場合、物件内での死亡を次の入居者に説明する義務を、告知義務といいます。
国土交通省のガイドラインでは、自然死や老衰などの死亡は原則として告知不要ですが、事件性がある死亡や特殊清掃を要した孤独死などは告知が必要です。
ただし、一定期間が経過し、再度賃貸として物件を借す場合は告知義務が免除されることもあります。
告知は、後のトラブルを防ぐためにも、書面で行うのが望ましいです。特に不動産取引で交付される重要事項説明書の記載で、内容を明確に伝えることができます。
告知の義務を怠ると、損害賠償にも及ぶケースがあるため、慎重に対応しましょう。
事故物件を隠して貸すと損害賠償請求のリスクがある

事故物件であることを告げずに契約をした場合、告知義務違反となり、重大なトラブルに発展する恐れがあります。
発覚からおおむね3年間は告知義務があり、借主は契約解除や敷金、礼金の返還を求めることも可能です。
さらに、心理的瑕疵により精神的苦痛や引越し費用などの損害賠償を請求されることもあります。
過去には、前の前の住人が室内で亡くなり特殊清掃を必要とした事案の部屋だったと、入居後に知った借主は「知っていたら契約しなかった」と主張し支払った金額の返金を求めた判例がありました。
このようなトラブルを未然に防ぐためにも、事故物件であることは正確に告知し、誠実な対応を心がけましょう。
告知義務が発生するケース

人の死に関する告知義務は、国土交通省が定めたガイドラインに詳細に示されました。不動産取引のトラブルを未然に防ぐことが目的です。
住宅用の物件では、過去に借りた物件で人が亡くなっていた場合、亡くなった内容によっては借主が契約を締結するか否かの重要な判断材料になる可能性が高いです。
貸主や売り主には、取引相手の判断に大きな影響を与える可能性がある事実は、誠実に伝える義務(信義則上の告知義務)があります。
心理的瑕疵とは
心理的瑕疵とは、不動産の設備や構造に問題がなくても、借主や買主が住むことに心理的な抵抗を感じる事情がある状態を指します。
例えば、室内で自殺や他殺、孤独死によって特殊清掃に至ったケースや周囲に墓地や嫌悪施設がある場合などが該当します。
こうした事情のある不動産物件には物件の価値に影響を及ぼすことがあり、ほとんどの方が住みたくないと感じるため、取引の際にはトラブル防止のためにも告知が重要です。
告知が必要となる条件
貸主や売り主は心理的瑕疵に該当する場合、重要事項として借主や買主に告知する義務があります。
告知が必要となる事案は以下のとおりです。
・人の死に関する事案:自殺、他殺、事故死など
・特殊清掃や大規模リフォームを伴った孤独死
・借主や買主からの特別な質問
・不動産取引に重要な影響を及ぼす可能性が高い事案
・共用部分での上記の事案
人の死のなかでも自然死や日常生活上の不慮の事故は原則告知義務はありません。
事件性や社会的な影響、周知性が高い事案などは、通常の基準に捉われず告知が必要です。借主が日頃使用する共用部分も該当します。
告知が必要となる期間
賃貸物件では、心理的瑕疵が発生してからおおむね3年間は、告知義務があります。ただし、事件性が高い場合は3年を超えても告知が必要とされることが少なくありません。
自然死や老衰は原則対象外ですが、長期放置や特殊清掃が行われた場合は、告知が必要です。
心理的瑕疵の感じ方は人それぞれ異なり、国土交通省が一定のガイドラインを定めていますが、事故物件の内容や受け止め方によって判断が分かれます。
貸主は、告知内容と告知期間を踏まえ、誠意をもって対応しましょう。
告知義務が発生しないケース

告知義務の線引きが曖昧で理解が難しいと感じる貸主も少なくありません。すべて伝えるリスクもあるのではないかと判断を誤ることは避けたいはずです。
告知義務が発生しないケースも国土交通省の宅地建物取引業者による人の死の告知に関する資料には記載されています。
トラブルの未然防止のために現時点(2021年10月)で妥当と考えられる一般的な基準をまとめたガイドラインになります。
自然死
誰にでも起こりうる自然な出来事であり、通常は心理的瑕疵とまではみなされないため老衰や持病による病死の場合、原則として貸主に告知する義務はありません。
例えば、高齢者が自宅で静かに亡くなったケースや家族や医療関係者が立ち会ったうえでの死亡は、告知の必要がないとされています。
ただし、遺体が長期間発見されずに腐敗が進行した場合など、特殊清掃が必要になるケースは例外です。
不慮の死

不慮の死とは日常生活のなかで誰にでも起こりえる突発的な事故を指します。例えば、自宅の階段からの転落や転倒、入浴中の溺死や食事中の誤嚥による窒息死などが該当します。
不慮の死は年齢を問わず誰にでも起こりうる一般的な事故です。
不慮の死は特殊な事情とはいえず、賃貸借取引の判断に重要な影響を及ぼす可能性は低いと考えられているからです。
ただし、自然死同様に長期間の放置によって腐敗などがあった場合はその限りではありません。
隣接住戸や日常生活で通常使用しない共用部分での死
死亡事故が隣の部屋や屋上などの共用部で発生した場合、原則として告知義務はありません。
入居者の生活空間と直接関係がなく、心理的な影響も限定的と判断されるためです。
例えば、立ち入りが制限された場所での事故は生活に支障を与える可能性が低く、重要な判断要素に該当しないとされます。
ただし、事故内容や周囲の状況によっては例外もあるため、専門家への相談を検討するのが望ましいでしょう。
成仏不動産では、不測の事態に備えて24時間365日メール対応が可能な体制を整えています。
特殊清掃から遺品整理はもちろん、各種法的手続きまで専門知識を持つ相談員が丁寧に対応し、あなたの悩みをじっくりお伺いします。
事故物件専門コンサルタントとして成仏不動産はワンストップサポートする企業です。
ぜひ一度、無料相談をご利用ください。
周囲の部屋の入居者には告知する必要がある?

法的には、日常的に使用しない共用部分で発生した死亡事故に告知義務はありません。
ただし、事件性や社会的影響が大きい場合は、共用部分であっても告知義務が生じる可能性があります。
告知義務は、不動産取引における心理的瑕疵の基準に基づいて判断されます。告知の際には、故人のプライバシーに十分な配慮が大切です。
例えば、故人や遺族の名前や年齢、住所と勤務先など個人が特定されるような個人情報は伝えないように注意しましょう。
基本的な告知義務はありませんが、周囲の入居者との信頼関係を保ち、トラブルを防ぐためにも相手に配慮した丁寧な説明を心がけましょう。
賃貸物件が事故物件になってしまった場合の客付けのポイント

賃貸物件が事故物件として扱われるようになり、オーナーにとっては資産価値の低下や家賃収入の減少は大きな損失につながります。
また、次に借り手が見つかるかどうかも大きな不安材料となるでしょう。
事故物件の入居者をスムーズに見つけるためには、価格的な魅力に加え、室内の清潔さやリフォームによる快適な住み心地も重要視されます。
具体的なポイントを解説していきます。
初期費用の値下げを行う
事故物件であっても、費用面で魅力を出すことで、価格重視の入居者希望者には十分にアピールできます。敬遠されがちな物件でも、借主が見つかる可能性が高まります。
賃貸物件契約時に必要な初期費用の負担軽減策として、敷金や礼金を値下げしたり、思い切って無料にしたりする方法が効果的です。
特に予算に限りのある若年層や単身者にとっては、大きな魅力となるでしょう。さらに、一定期間の家賃が無料になるフリーレントを導入するのもおすすめです。
例えば、一ヶ月家賃無料などの制度は実質的な入居コストを抑えることができるため、初期費用を気にする入居者の目に留まりやすくなります。
家賃の値下げを行う

家賃を相場より下げることは、事故物件の空室対策として効果的な方法の一つでしょう。
値下げ幅は、相場の2〜3割安程度が一般的ですが、場合によって半額近くまで下げるケースもあります。
同じエリアで家賃が安い物件を探している入居希望者にとって、事故物件は住めれば十分と考える傾向があり、コスト重視の層からの需要が期待できます。
ただし、一度下げた家賃はもとに戻すのが難しいこともあるため短期的な入居の目的だけでなく、中長期的な収益計画も見据えた判断が大切です。
清掃やリフォームをしっかりと行う
内装や設備を一新し、場合によっては周辺物件よりクオリティを高く仕上げることで、価格の安さだけでなく思った以上に快適な部屋の印象が付きます。
事故物件の印象を払拭し、コストパフォーマンスの高い掘り出し物として魅力を打ち出すことも可能です。
特にリフォームを行う際は「事故物件だから仕方なく直した」と消極的な印象ではなく、住みやすい空間をより意識して改装したことを強調しましょう。
オーナー側の前向きな姿勢が、入居希望者の不安を和らげ、安心感をもって検討してもらえる後押しになります。
事故物件の対処にお困りなら

突然、所有物件が事故物件になり、どう対応すべきか迷う貸主の方も少なくありません。しかし、誰にでも起こりうるケースです。
一人で悩まず、専門家に相談して的確なサポートを受けることで、事故物件となった状況でも再び入居者を迎えられる道が開けます。
成仏不動産では事故物件に特化した専門家として、今までたくさんの物件に向き合い、貸主のサポートをしてきました。
物件の状態はそれぞれ異なるため、物件一つひとつの状況を精査し、清掃・リフォーム・告知義務判断・再募集サポートまで一貫して対応をしております。
経験豊富なスタッフが丁寧に対応しますので、お気軽にご相談ください。全国どこからでもご相談いただけます。まずは無料相談をご利用ください。