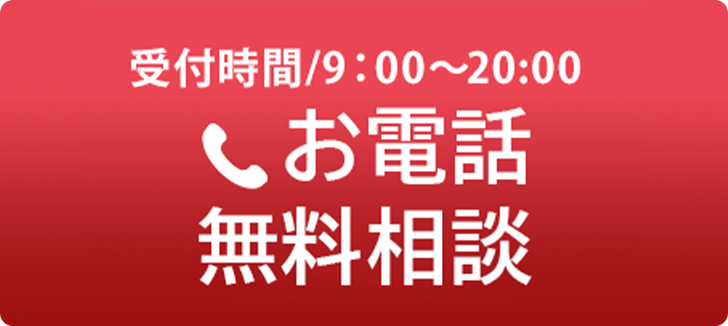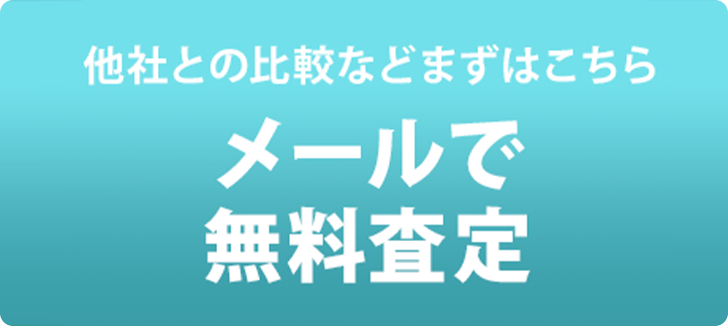心理的瑕疵のある事故物件とは?瑕疵の種類や告知義務期間、売却について解説
2025年9月16日

心理的瑕疵のある事故物件とは、物件そのものの機能不全や法律違反はなくとも、住む方に嫌悪感や不安を与える状態にある事故物件のことです。
所有している不動産が心理的瑕疵のある事故物件にあたる場合、売却の決断はとても悩ましい問題です。
「売りたいけれど、トラブルにならないか不安」「どこまで説明すればよいかわからない」という声も多く耳にします。
しかし、心理的瑕疵があっても、正しい知識を持って適切に対応することで売却は可能です。
本記事では心理的瑕疵の定義や告知義務の基準、売却方法、注意点を詳しく解説します。無事に売却できるか不安を抱えているという方は、ぜひ参考にしてみてください。
事故物件とは

「事故物件」という言葉は耳にしたことがあっても、具体的な内容を知らない方も多いでしょう。事故物件の定義を知ることは、自分の所有する物件が該当するかを判断する第一歩です。
こちらでは、はじめに事故物件の定義を説明し、事故物件が不動産価値に与える影響についても詳しく解説します。
事故物件の定義
事故物件とは、物件内やその周辺で過去に事件や事故が発生し、心理的な嫌悪感を持たれやすい物件を指します。
例えば、自殺や他殺、孤独死など人の死が関連するケースです。また、火災や事故が原因で居住者が死亡した物件も該当する場合があります。
さらに、物件の近隣で発生した事件や反社会的勢力の関与も含まれることがあります。事故物件に該当するかどうかは、買主や借主に対する心理的な影響の有無で判断されるものです。
事故物件が不動産価値に与える影響

事故物件は一般の物件と比較して不動産価値が下がる傾向にあります。買主や借主にとって「住みたくない」と思わせる要因が、価格や需要に大きな影響を及ぼします。
特に心理的瑕疵が告知されると、買主が避けがちになり売却まで時間がかかることもあるでしょう。
不動産価値の低下を防ぐためには、告知義務や適切な売却手順を正しく理解したうえで対応するようにしましょう。
事故物件の売却で悩んでいるなら、私たち成仏不動産にお任せください。
私たちは、自殺・孤独死・事件など心理的瑕疵のある物件や、他社が敬遠しがちな訳あり不動産を専門に扱うプロ集団です。単なる仲介ではなく、「どんな物件でも前向きに解決策を提示する」対応力が私たちの大きな強みです。
売却だけでなく、特殊清掃・遺品整理・供養・相続手続きまでワンストップで対応可能で、ご相談者様の気持ちに寄り添い、安心感を持って任せられるサポート体制を整えています。
全国どこからでも無料でご相談可能です。まずは私たちにご相談ください。
心理的瑕疵とは

不動産取引において瑕疵とは、通常想定される品質や状態に欠陥があることを指します。
なかでも心理的瑕疵は物件そのものの機能不全や法律違反ではなく、住む方に嫌悪感や不安を与える事実です。
具体的には物件内外での死因を伴う事故や事件の履歴、反社会的勢力や風俗店の近接などが該当します。
これらは実際の建物構造や法令適合とは別軸で判断され、告知義務の対象となる重要な要素です。
心理的瑕疵を正しく理解し告知することで、買主や借主とのトラブルを未然に防げます。
心理的瑕疵の定義
心理的瑕疵とは、住環境に心理的嫌悪感を抱かせる事実を指す言葉です。
例えば人の死が発生していたり、付近に墓地や嫌悪を感じる施設が立地していたり、近所に反社会的勢力(暴力団)が居住していたりといった例が挙げられます。
物件が原因で心身にストレスを与える恐れがある場合、法律的に告知義務が発生します。定義上は物件の瑕疵といっても、構造や設備の瑕疵とは異なる性質を持つ点が特徴です。
ほかの瑕疵との違い
不動産取引における瑕疵には、心理的瑕疵のほかに以下の3種類が挙げられます。
・環境的瑕疵
・物理的瑕疵
・法的瑕疵
環境的瑕疵は騒音、悪臭、周辺施設の影響など生活環境の問題です。また、物理的瑕疵は建物や設備の欠陥を指し、雨漏りや耐震性不足などが該当します。
法的瑕疵は違法建築や権利関係の問題を意味し、違法増築や境界紛争が該当する瑕疵です。
取引時には各瑕疵を区別し、それぞれに応じた告知義務や対応策を取る必要があります。
心理的瑕疵の判断基準

心理的瑕疵は、物件にまつわる出来事が住まい手に不安や嫌悪感を与えるかで判断されます。
2021年10月に国土交通省によって定められた宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドラインでは、以下のような事例が心理的瑕疵として買主や借主へ告知義務が必要であると定められています。
・殺人
・自殺
・特殊清掃を必要とする自然死
・特殊清掃を必要とする不慮の事故による死
・不慮の事故といえない事故死
・原因不明の死
具体的には物件内での死亡事案があったかどうかがまず重要です。孤独死や自殺などが発生し、発見までの期間が長い場合は心理的瑕疵になりやすいとされます。
次に事件や事故が起きた場所がマンションでいう専有部分か共用部分かもポイントです。玄関先やエレベーター内での事案は共用部分扱いになることもあります。
また、発見後に特殊清掃や大規模リフォームが行われたかも判断材料のひとつです。清掃やリフォームの痕跡が住む方に心理的負担を与える場合があるためです。
隣接家屋や近隣で重大事件が起きた場合も、物件に及ぼす心理的影響を考慮する必要があります。
例えば近隣で殺人事件があったときは購入者が嫌悪感を抱きやすいとされます。反社会的勢力の拠点や風俗店など嫌悪施設が近接しているかも重要です。
これらはガイドラインで、社会的影響の大きい事案として位置づけられています。さらに、物件が周囲に及ぼすイメージや風評被害の可能性も判断基準に含まれます。
例えば、団地全体が事故物件として知られると、他住戸にも影響が広がってしまうでしょう。国土交通省のガイドラインにはこれらの視点が網羅的に示されており、詳細な判断基準が記載されています。
これらを手がかりにご自身の物件を当てはめ、適切に対応することが大切です。
心理的瑕疵の具体例

心理的瑕疵の判断基準がわかっても、自分の物件に当てはまるかはイメージしにくいものです。心理的瑕疵のある物件は、以下のような具体例が挙げられます。
・事件や事故で物件内で人が死亡したケース
・事件や事故で物件周辺で人が死亡したケース
・物件周辺に反社会的勢力の拠点が所在するケース
・物件周辺に風俗店や刑務所などの嫌悪施設が所在するケース
ここではガイドラインに沿った代表的な事案を紹介し、具体例を通じて理解を深めていきます。
事件や事故で物件内で人が死亡したケース

物件の居室など専有部分で自殺や孤独死が発生した場合は、典型的な心理的瑕疵です。
特に発見まで時間が経過して腐敗が進んだケースは、告知義務の対象になりやすいとされています。
特殊清掃やリフォームによって死後の痕跡が消えていても、発生事実自体は告知しなければなりません。
買主は当該場所での死亡を知ることで居住に対する抵抗感を抱く可能性が高いためです。たとえ事故から年月が経っていても、専有部分であれば告知免除が認められにくい傾向にあります。
事件や事故で物件周辺で人が死亡したケース
物件の敷地外や隣接地で事件事故が起きた場合も、心理的瑕疵と判定されることがあります。
例えば玄関前や共用廊下、敷地内駐車場で人が死亡したケースは、周辺事案として告知が必要です。
近隣住戸での殺人や交通事故死などが近接し、視界に入る範囲で起きた場合は居住者が嫌悪感を抱きやすい傾向です。
敷地全体や建物のイメージが損なわれるため、周辺環境の一部と見なされて告知義務の対象になります。
周辺事案の範囲や距離感は、ガイドラインの判断材料を参考に慎重に見極める必要があります。特に事件性や社会に与えた影響が大きい事案は、告知義務の程度が高いといえるでしょう。
物件周辺に反社会的勢力の拠点が所在するケース
近隣に暴力団事務所や反社会的集団の拠点があると、心理的瑕疵として告知が求められる場合があります。
犯罪行為の温床とされる施設が近くにあることで、安全性や街のイメージが大きく損なわれるからです。
たとえ当該施設が表向きは集合住宅やビルとして運営されていても、周辺住民の不安を招くと判断されます。
ガイドラインでは社会的影響の大きさや住民の受け止め方を重視しているため、告知義務になることが多い傾向です。
開示しないままで売却すると、後になってトラブルや法的責任を問われるリスクが高まるため注意しましょう。
物件周辺に風俗店や刑務所などの嫌悪施設が所在するケース
風俗店や刑務所など一般的に嫌悪感を持たれる施設が近隣にある場合も、心理的瑕疵とされます。
こうした施設は生活環境にネガティブな影響を及ぼすとされ、買主の居住意欲を著しく低下させるためです。
ガイドラインではこれらを公衆衛生上または環境上の著しい支障を生ずる施設と位置づけ、告知を求めています。
近接距離や施設の規模、利用時間帯なども判断材料となるため、専門家に相談しながら見極めましょう。
売却前に事実を開示し対応策を講じることで、トラブル回避と信頼構築につながります。
心理的瑕疵のある物件を売却したいけれど、何から手を付ければよいのかわからない方は、ぜひ私たち成仏不動産にご相談ください。
成仏不動産は、心理的瑕疵物件や相続物件など、一般的な不動産会社では敬遠されがちな物件を専門に扱うプロフェッショナルです。法的な手続きや査定の根拠も明確に提示し、安心感を持って進められる環境をご用意しています。
事故物件を巡る不透明さや偏見をなくし、誠実な情報開示と的確なサポートで売主様と買主様の信頼関係を築きます。
まずはお気軽にご相談ください。
宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドラインとは

宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン(以下ガイドライン)とは、2021年に国土交通省が定めた、事故物件の告知基準をまとめたガイドラインです。
こちらは不動産取引にあたり、取引対象の不動産で生じた人の死について告知に係る判断基準がないことによりトラブルが多数発生していたのを受けて定められました。
ガイドラインでは専有部分での死亡発生や特殊清掃の履歴を告知対象と定めています。 また、大規模リフォームの有無や事故発生からの経過期間についても基準が示されました。
賃貸取引と売買取引で告知義務の範囲や期間に違いがある点も明記されています。
大きな特徴は、心理的瑕疵の判断を社会的影響や物件状況に応じて行う点です。 これにより従来曖昧だった取引ルールの透明性が大きく向上しました。
買主や借主はガイドラインを根拠に物件選びができ、安全性が確保されます。売主や仲介業者も基準に沿って説明責任を果たしやすくなるため、トラブル予防につながります。
心理的瑕疵の告知義務があるケース

心理的瑕疵の、告知義務が必要なケースは、大きく分けて以下の3つです。
・特殊清掃や大規模リフォームが行われた場合
・買主・借主から瑕疵の確認があった場合
・社会的影響の大きい事案の場合
以下で詳しく解説するので、自身の物件が該当するか確認してみましょう。
特殊清掃や大規模リフォームが行われた場合
物件内で死亡事案があった際に、特殊清掃や大規模リフォームを行った場合は告知義務があります。
特殊清掃の跡やリフォーム痕は心理的負担を生みやすいため、買主や借主に正確な情報を開示する必要があります。
特に清掃範囲やリフォーム内容は詳しく説明し、透明性を確保すると安心感が高まるでしょう。隠蔽とみなされれば法的トラブルに発展するリスクもあるため注意が必要です。
買主・借主から瑕疵の確認があった場合
買主や借主から物件の経緯や事故の有無について質問があった場合は、経過年数に関わらず告知義務が発生します。
瑕疵の有無を問われた際は事実を正確に伝え、詳細を説明することが信頼構築につながるでしょう。
書面での回答や重要事項説明書への記載も忘れず行っておくと、後のトラブルを防ぐことが可能です。曖昧な回答や隠蔽があると、契約不適合責任を問われる恐れがあるため注意しましょう。
社会的影響の大きい事案の場合
有名人の自殺や地域で大きく報道された凶悪事件など、社会的注目度が高い事案は告知義務の対象です。
マスコミ取材やSNSで話題化したケースは、周辺住民や購入希望者への影響が大きいため、通知が求められます。
告知内容やタイミングはガイドラインを参考に慎重に決定し、書面で明示することで信頼性を担保しましょう。
自分の持っている物件が心理的瑕疵の告知義務に該当するのか判断できず、不安を抱えていませんか?
そんなときは、事故物件の専門家である私たち成仏不動産にご相談ください。
成仏不動産は、事故・事件・孤独死などによる心理的瑕疵のある物件を数多く取り扱ってきました。法令を遵守し、正しい基準で判断したうえで、価値ある物件として次の持ち主へと引き継ぐための適切な方法をご提案します。
まずは無料相談で、私たちにお悩みをお聞かせください。
心理的瑕疵の告知義務が免除される可能性のあるケース

心理的瑕疵の告知義務は原則として厳格ですが、例外も存在します。ガイドラインには「一定の条件を満たした場合は告知が免除される」と明記されています。大きく分けると、以下の3つのケースです。
自然死や不慮の事故死による死亡があった場合
死亡事故から3年以上経過している場合
共用部分や隣接住戸で死亡が発生した場合
以下では主な免除要件を詳しく解説し、ご自身の物件が該当するか確認するポイントをご紹介します。
自然死や不慮の事故死による死亡があった場合
自然死とは疾病や老衰などによる死亡を指し、一般的には心理的瑕疵の対象外です。また、不慮の事故死も外部要因による偶発的な死亡と判断され、告知免除となるケースが多くなります。
ただし、火災や転落などが原因の事故死は事故物件として扱われる場合があります。特に不動産業者や宅地建物取引業法に基づく告知義務の判断が変わる可能性があるのは、建物が火元となった火災死や高所からの転落死、あるいは第三者の関与が疑われる場合です。
このような場合は、事例ごとに慎重な対応が欠かせません。物件内外の状況や近隣住民の証言、現場写真などあらゆる証拠を集め、事故の詳細な経緯を把握しましょう。
そのうえで売主、貸主は医師による死亡診断書や警察の検分書や調書を取得し、自然死か事故死かを判断します。さらには事故死であればその原因や時間、場所などの事実関係を明確化することが重要です。
これらの書類は、取引の安全性や信頼性を高める根拠資料となり、トラブルを未然に防ぎます。
死亡事故から3年以上経過している場合

死亡発生から一定期間が経過すると心理的嫌悪感が薄れるとされ、告知が免除される可能性があります。
ガイドラインではおおむね3年を目安としていますが、地域性や事件内容によって変動することもあります。
心理的な負担が残っていないかの判断においては、不動産業者内部での事例共有や、業界団体が発行するリスク評価シートを活用することで、より客観的な判断材料をそろえられます。
さらに、賃貸物件で発生から3年以上経過している場合でも、内見時に問い合わせがあれば正直に回答してトラブル回避に努める必要があります。
共用部分や隣接住戸で死亡が発生した場合
物件専有部ではなく共用廊下や駐車場などで死亡事故が起きたケースは、告知免除となる場合があります。
また、隣接住戸での死亡も直接的な居住空間とは異なるため、免除対象として扱われるのが一般的です。
ただし、発生場所が生活動線上にあったりリフォーム痕跡が見えたりする場合は、購入者に嫌悪感を与える可能性があります。
共用部分や隣接住戸での事案も、発生から3年以上経過している場合と同様に、内見の際などに問い合わせがあったら事実を説明する姿勢を持ちましょう。トラブル回避のためには、誠実な対応がなによりも肝要です。
心理的瑕疵のある事故物件を所有するリスク

心理的瑕疵のある事故物件を放置すると、さまざまなリスクを抱えることになります。まず、売却価格が周辺相場より大幅に下がる可能性が高いです。
長期間市場に出し続けても買い手がつかず、売れ残るリスクもあります。物件が長期間売れ残ることで、「何か問題があるのでは」と余計に敬遠される負のスパイラルに陥りやすいです。
さらに事故物件の所有が長引くほど固定資産税や管理費などの維持コストがかさみます。
修繕やリフォームに投資しても、心理的瑕疵を理由に価値回復が難しいケースも少なくありません。
また、告知義務を果たしていない場合は契約後にトラブルに発展する可能性があります。買主や借主から重大な損害賠償を請求されるリスクも否定できません。
このように事故物件を適切に処理しないと資産価値の毀損が加速し、手放すことすら困難になります。心理的瑕疵のある物件を所有するリスクを把握し、早めに対処しましょう。
以上のような心理的瑕疵のある事故物件をそのまま所有し続けるリスクを減らすためにも、成仏不動産にご相談ください。
成仏不動産は、心理的瑕疵のある事故物件を専門的に扱う不動産のプロとして、現場での強力消毒や特殊清掃、遺品整理までを一括で行い、次の持ち主に引き継げる状態へと整えています。
さらに、神社や寺院での供養を行った物件には「成仏認定書」を発行し、買い手に安心感を与える付加価値を提供します。相続や法的な手続きもワンストップで対応できるため、複雑な問題もまとめて解決可能です。
心理的瑕疵のある事故物件の売却でお悩みの方は、まずは無料相談でお気持ちをお聞かせください。
心理的瑕疵のある事故物件の告知義務期間

売買や賃貸において、いつまで心理的瑕疵を告知すべきかというのは重要な判断基準です。告知義務期間は賃貸と売買で扱いが異なります。
以下では、心理的瑕疵のある事故物件の告知義務期間を、賃貸と売買それぞれ解説します。
賃貸の場合
賃貸取引では、おおむね3年が心理的瑕疵の告知義務期間の目安です。これは事故発生から時間が経過すると入居者の心理的負担が和らぐという考えに基づきます。
ただしガイドラインはあくまで目安であり、事案の社会的影響度や地域性によって変動するため注意が必要です。
例えば著名人の自殺やマスコミ報道が大きかった事案は、3年を超えても告知が必要になるケースがあります。
また、入居希望者から明確に確認があった場合には期間を問わず正確に回答する義務があります。
賃貸借契約を結ぶ際は、契約書に心理的瑕疵に関する条項を設け、丁寧に説明しましょう。
売買の場合
売買取引では、心理的瑕疵が買主の判断に影響するかが告知義務の基準となります。そのため、一定の年数で一律に告知義務が消滅するわけではありません。
時効的に告知義務が消滅するような法律も存在せず、買主保護の観点が優先されます。一般的には5年または10年程度が目安とされますが、物件や地域で異なる判断が必要です。
売主は発生事実を正確に開示し、買主が納得したうえで契約を進める姿勢が求められます。 事前に不動産業者や専門家に相談し、適切な告知期間と方法を確認しましょう。
心理的瑕疵のある事故物件を売却する方法

事故物件の売却には、仲介による売却と買取という2つの手段があります。
それぞれにメリットとデメリットがあるため、物件状況や売却希望時期に応じて選択しましょう。
仲介による売却
仲介売却は市場に公開して買主を探す方法です。市場価格で売却できる可能性があるため、買取よりも価格が下がりにくい特徴があります。
適切に告知義務を履行し瑕疵を価格に反映すれば、買主の納得を得やすいです。
しかし、売却までに時間がかかるといったデメリットもあります。心理的瑕疵のある物件は買い手が限定されるため、成約までに数ヶ月から年単位でかかることもあります。
また、売却活動中に価格交渉が発生し、想定より低い価格での成約になるケースもあるでしょう。
活動を効率化するには、事故物件の取扱いに慣れた専門の不動産業者を活用することがおすすめです。
買取
買取は不動産会社に物件を直接買い取ってもらう方法です。メリットは売却スピードが大変速い点です。
売却活動の手間や告知作業を一括で任せられるうえ、短期間で現金化できます。
デメリットは売却価格が相場より下がる点です。買取業者は心理的瑕疵リスクを織り込んだ金額を提示するため、価格交渉の余地が小さくなります。
価格よりも早期現金化を優先する場合は買取がおすすめです。
複数の買取業者から見積もりを取り比較することで、適切な価格と条件を得られるでしょう。
心理的瑕疵のある事故物件売却時の注意点

事故物件の売却には、以下のような注意点があります。
・相場より低価格での売却となる傾向がある
・告知義務をきちんと履行する
・瑕疵保険の加入を検討する
・リフォームや修繕による印象改善を図る
これらを把握し事前準備を徹底することで、トラブルを防ぎましょう。以下で詳しく解説します。
相場より低価格での売却となる傾向がある
心理的瑕疵がある物件は、一般的に相場より低い価格設定になりやすいです。市場に出す際は周辺相場と立地条件を考慮しつつ、現実的な販売価格を設定しましょう。
高すぎる価格設定は売れ残りのリスクを高めますが、安すぎると損失が拡大します。不動産業者と相談し、適切な価格レンジを見極めることが重要です。
告知義務を確実に履行する

告知義務を怠ると、契約解除や損害賠償など法的リスクが発生します。購入者に対して書面や重要事項説明書を用いて事実を開示し、合意を得ることが必須です。
口頭だけでは後のトラブルを防ぎにくいため、必ず書面での告知を行いましょう。
リフォームや修繕による印象改善を図る
売却前に、物件内部の清掃や設備交換など、リフォームで第一印象を改善することも重要です。
心理的瑕疵そのものは消せませんが、清潔感や快適性を高めることで買主の抵抗感を和らげます。
内見時にはリフォーム履歴やメンテナンス記録を提示し、信頼性をアピールしましょう。
告知義務を怠るとどうなるか

心理的瑕疵を含む瑕疵の告知義務を怠ると、以下のようなリスクがあると考えられます。
・契約を解除される可能性がある
・損害賠償請求を受ける可能性がある
・契約不適合責任を問われる可能性がある
以下で詳しく解説します。
契約を解除される可能性がある
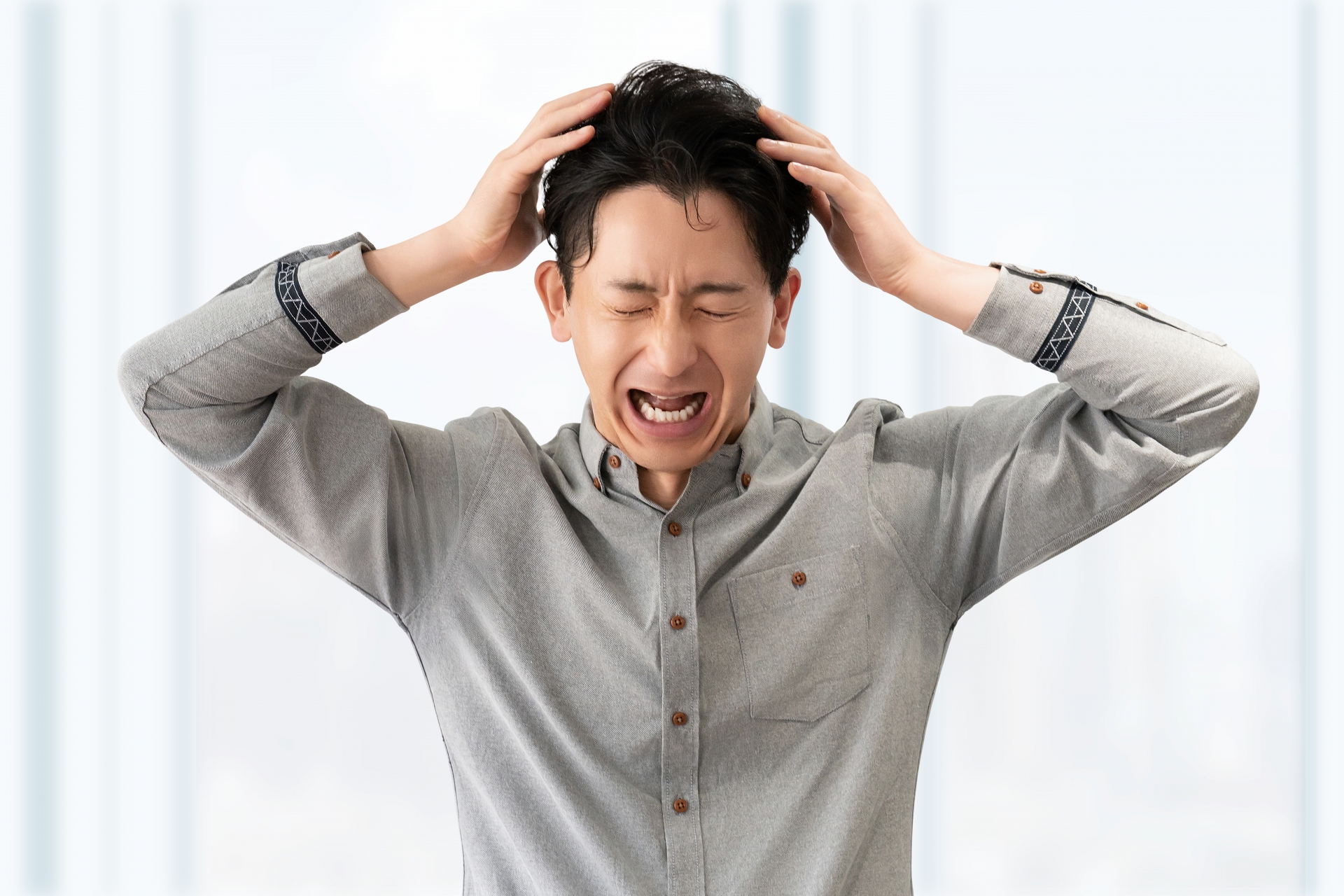
買主が取引後に心理的瑕疵を認識した場合、契約解除を申し出る権利を持つため、売主は買主の解除申請を拒否できません。
その結果、すでに受け取った手付金や売買代金の返還義務が生じてしまいます。
契約解除が成立すると売主側は再度の売却活動を余儀なくされるため、大きな機会損失が発生します。
特に売却先の探索コストや時間が重複し、経済的にも精神的にも大きな負担になるでしょう。
損害賠償請求を受ける可能性がある
告知義務違反が判明すると、買主は精神的苦痛や引越し費用などを理由に損害賠償を請求できます。
裁判で不実告知が認められれば、売主は高額な賠償金の支払いを命じられる可能性があります。
実際に裁判費用や弁護士費用も別途負担となり、さらに買主との和解交渉に多大な時間を割かれ、本来の業務に支障をきたすケースも考えられるでしょう。
契約不適合責任を問われる可能性がある
2020年の民法改正により、瑕疵担保責任は契約不適合責任に変更されました。
契約内容に反する事故物件の心理的瑕疵は契約不適合と見なされ、売主は修補や代金減額の請求に応じなければなりません。
また、契約不適合責任を履行しない場合は裁判で強制され、さらに損害賠償責任を追加で負うリスクがあります。
責任期間は引渡し後一定期間と法定で定められており、売主はその期間中に瑕疵を補う義務を負います。
売主が告知を怠ると免責条項も無効となり、法的救済が厳しくなる点に注意が必要です。
心理的瑕疵のある事故物件のトラブルを避けるためにできること

心理的瑕疵のある事故物件を売却する際、トラブルを避けるためには対策が重要です。具体的には、以下の3点を押さえる必要があります。
・ガイドラインをしっかりと理解しておく
・説明責任を誠実に果たす
・プロに相談し適切に対応する
以下では、こちらの3点を詳しく解説します。トラブルを避けて無事に物件を売却するためのヒントとしてお役立てください。
ガイドラインをしっかりと理解しておく
国土交通省のガイドラインを熟読し、告知義務の基準や期間を把握しましょう。判断に迷う事案はガイドラインの該当箇所を確認し、根拠を明確にしておくことが重要です。
説明責任を誠実に果たす
買主に対して心理的瑕疵を含むすべての事実を丁寧に説明することも重要です。口頭だけでなく書面での告知と重要事項説明を徹底し、後から争いが起きにくい体制を整えましょう。
プロに相談し適切に対応する
自分ひとりでは不安だという方は、不動産取引の専門家や弁護士に早い段階で相談しましょう。専門家のアドバイスを受けることで、適切な告知方法や売却戦略が得られます。
プロへの相談を検討されている方は、ぜひ私たち成仏不動産にご連絡ください。
心理的瑕疵物件を専門に扱う私たちは、強力消毒や特殊清掃、遺品整理までを一括で行い、物件を売却可能な状態へ整えます。
さらに、無料相談から現場対応、売買までを一貫してサポートし、複雑な手続きもスムーズに進められる体制を整えています。
まずはお気軽に、私たちにお悩みをお聞かせください。
心理的瑕疵のある事故物件の売買についてプロに相談したいなら

心理的瑕疵がある物件の売却は知識と経験が必要なものです。そのため、一般の方にとっては大きな負担となってしまうこともあるでしょう。
事故物件の売却に悩んでいる方は、ぜひ成仏不動産へご相談ください。
私たちは2019年のサービス開始以来、6,200件以上のご相談に対応してきました。自殺や孤独死、殺人が発生した物件から、長年放置されたゴミ屋敷まで、あらゆる訳あり物件を解決へ導いてきました。
法律やガイドラインに精通した専任スタッフが、告知義務の判断・書面作成・特殊清掃や供養・相続手続き・価格設定・売買までワンストップで対応可能です。さらに、他社で値が付かなかった物件でも正しい査定で価値を見いだし、高額買取に挑戦しています。
全国どこからでも無料でご相談いただけますので、複雑な手続きや不安を一人で抱え込まず、まずは成仏不動産に現状をお聞かせください。