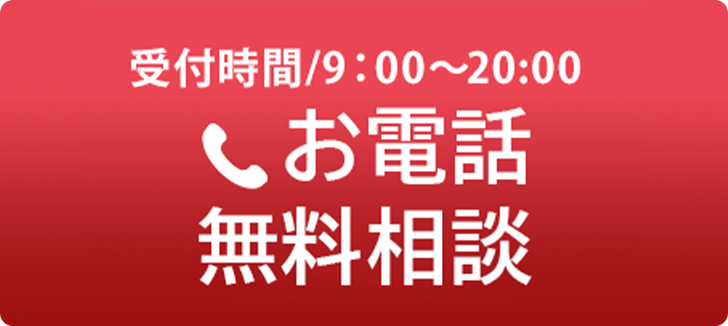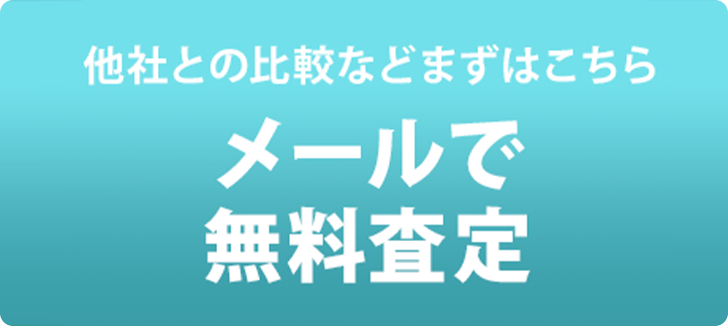事故物件の告知義務はいつまで?ガイドラインの内容や売買への影響も解説
2025年9月18日

事故物件を相続や購入で所有することになった場合、売却時に事故について話す必要があるのか、どこまで伝えればよいのか疑問を抱く方は少なくありません。
実は、事故物件の売却には国土交通省が定める明確なガイドラインが存在しており、適切に対応すればトラブルを避けて売却を進めることができます。
この記事では、事故物件の告知義務やガイドラインの内容を詳しく解説しています。正しい知識が身につき、状況に応じた売却方法が選択できるようになるでしょう。
事故物件とは

事故物件とは、過去に死亡事故などが発生した不動産を指します。しかし、すべての死亡事故が事故物件に該当するわけではありません。
一般的に事故物件として扱われるのは、自殺や他殺、事件性のある死亡や長期間発見されなかった孤独死などのケースです。
これらの死亡は、買主や借主の心理的な負担となる場合があるため、心理的瑕疵として扱われます。一方で、老衰や病気による自然死は原則として事故物件には該当しません。
事故物件かどうかの判断は、単純に死亡があったかどうかではなく、買主の購入判断に影響を与える可能性があるかという観点から行われます。
つまり、事故物件とは、一般の方が避けたいと感じるような死亡事故があった物件です。
事故物件の告知義務とは

事故物件の売却や賃貸において、売主や貸主が買主・借主に対して事故の内容を伝える義務を告知義務といいます。この告知義務は、不動産取引における重要な責任の一つです。
告知義務の概要
告知義務の基本的な考え方は、買主や借主が物件選択の判断をする際に、重要な情報を提供することにあります。
事故物件であることを知らずに購入や賃借をした場合、後からその事実を知った買主・借主が精神的な苦痛を受ける可能性があるためです。
宅地建物取引業法では、不動産業者に対して重要事項説明の義務を課しており、このなかに心理的瑕疵の告知も含まれています。
つまり、事故物件の売却を仲介する不動産業者は、買主に対してその旨を説明しなければなりません。告知義務の判断基準として、社会通念上多くの方が購入や賃借を躊躇するような事故については告知が必要になります。
告知義務が必要な理由
告知義務が設けられている理由は、主に3つあります。まず、買主・借主の知る権利を保護するためです。不動産は高額な買い物であり、購入や賃借の判断に影響する情報は、事前に知らされる必要があります。
次に、不動産取引の透明性の確保です。重要な情報が隠されたまま取引が行われると、後々トラブルの原因となります。最初から適切な情報開示を行うことで、双方が納得したうえでの取引が可能になるでしょう。
最後に、売主・貸主が法的リスクを回避するためです。告知義務を怠った場合、損害賠償請求や契約解除などの法的責任を問われる可能性があります。
適切な告知を行うことで、こうしたリスクを回避できます。
宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドラインの策定背景

2021年10月、国土交通省は宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドラインを策定しました。このガイドラインが作られた背景には、告知義務基準の曖昧さによる問題があります。
どのような死亡に告知が必要なのか、いつまでの期間告知すべきなのか、明確な基準が存在しませんでした。
そのため不動産業者によって対応がバラバラで、売主はどこまで話せばよいのかわからず不安を抱え、買主は本当に必要な情報が伝えられているのか疑問を持つことになりました。
また、裁判でも判断基準がないため、同じような事案でも判決が異なります。こうした問題を解決するため、国土交通省は有識者による検討会を設置し、統一的なガイドラインを策定しました。
ガイドラインに法的拘束力はありませんが、業界の指針としてより透明で公正な不動産取引を図ることとしています。
告知義務の期間はどこまで求められるか

告知義務の期間は、賃貸住宅と売買契約で異なる基準が設定されており、取引形態ごとの基準はガイドラインでの確認が必要です。
賃貸住宅の場合
賃貸住宅における告知義務の期間は、おおむね3年間とされています。賃貸住宅の場合、入居者が短期間で入れ替わることで、時間の経過とともに心理的な影響が薄れると考えられるためです。
ただし、この3年間という期間は絶対的なものではありません。メディアで大きく報道された事件や、地域社会に強い印象を残した事故には、より長期間の告知が求められます。
また、買主・借主から直接質問があった場合は、正直に答える必要があります。積極的な情報開示が求められているからです。
売買契約の場合
売買契約では賃貸と異なり、明確な期間の上限は設けられていません。これは、不動産の購入が一般的に長期間の所有を前提としており、賃貸よりも慎重な判断が求められるためです。
売買の場合、告知義務は買主の購入判断に重大な影響を与えます。つまり、何年前の事故であっても、それが買主に影響を与えるのであれば告知が必要です。
実際の判断では、事故の内容や発生からの経過年数、物件の状況や地域での認知度などが総合的に考慮されます。
例えば、10年前の事故であっても地域で広く知られている場合や、インターネット上に情報がある場合は告知が必要とされるでしょう。
事故物件の告知義務内容
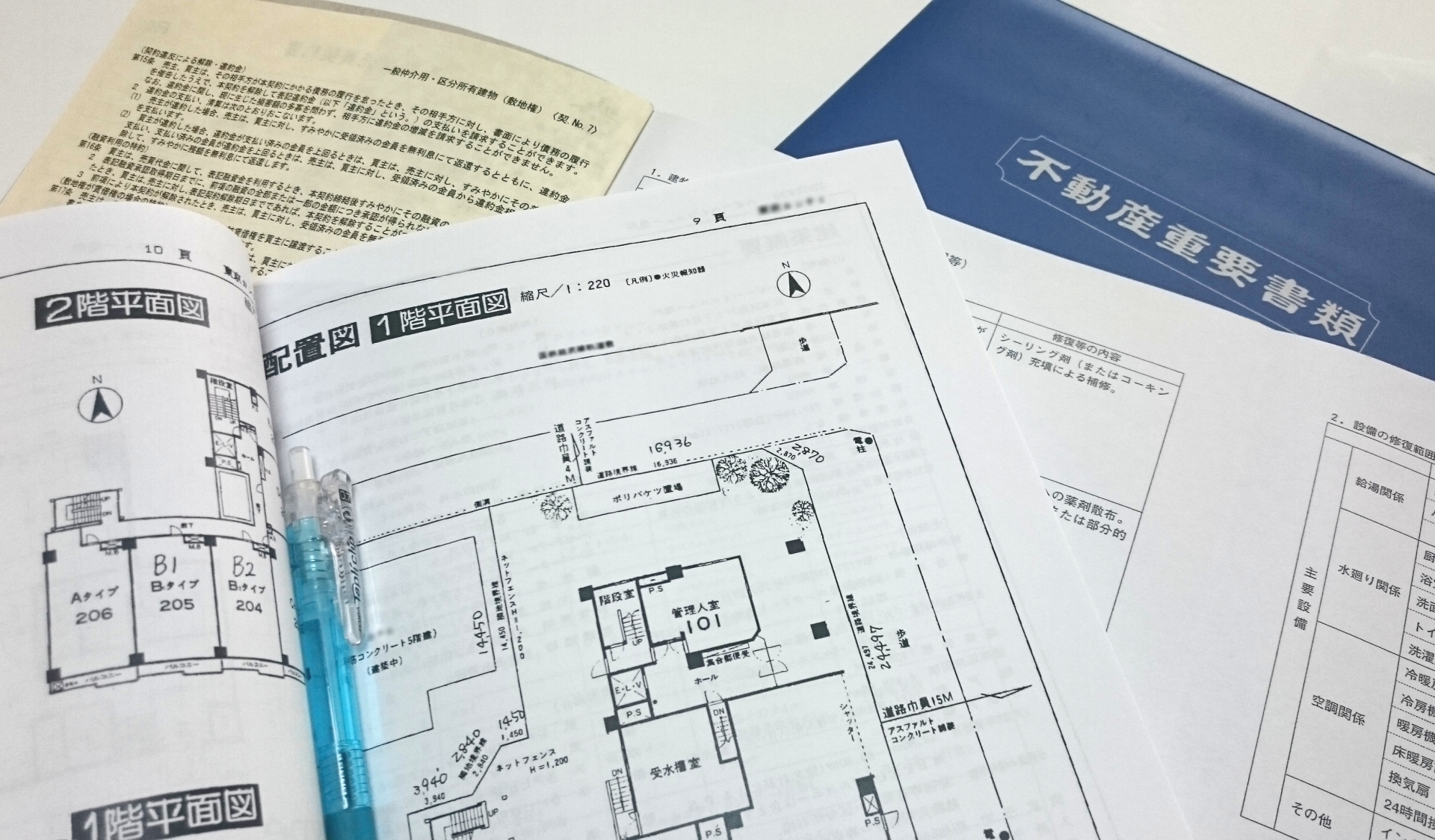
事故物件の告知を行う際は、適切な情報を適切な方法で伝える必要があります。ガイドラインでは、告知すべき具体的な内容について詳しく定められています。
発生時期
事故が発生した時期には、日付まで特定する必要はありません。〇年〇月頃や〇年前といった程度の情報で十分とされています。
ただし、あまりにも曖昧な表現は避けるべきです。数年前やしばらく前などの表現では、買主が適切な判断を下すことができません。
少なくとも年単位での時期は明確にする必要があります。また、複数回の事故が発生している場合は、それぞれの発生時期を伝える必要があります。
重大な事故のみを告知し、ほかの事故を隠すことは適切ではありません。
発生場所
事故が発生した場所は、室内の具体的な場所まで特定する必要があります。居室内・浴室内・玄関付近など、買主が状況を理解できる程度の詳細さが必要になります。
特に寝室やリビング、浴室などで発生した事故には、より詳細な説明が必要です。一方、ベランダや庭など居住空間から離れた場所での事故は、詳細な説明までは求められません。
共用部分や敷地外での事故には、原則として告知義務がありませんが、買主から質問があった場合は正直に答える必要があります。
死因
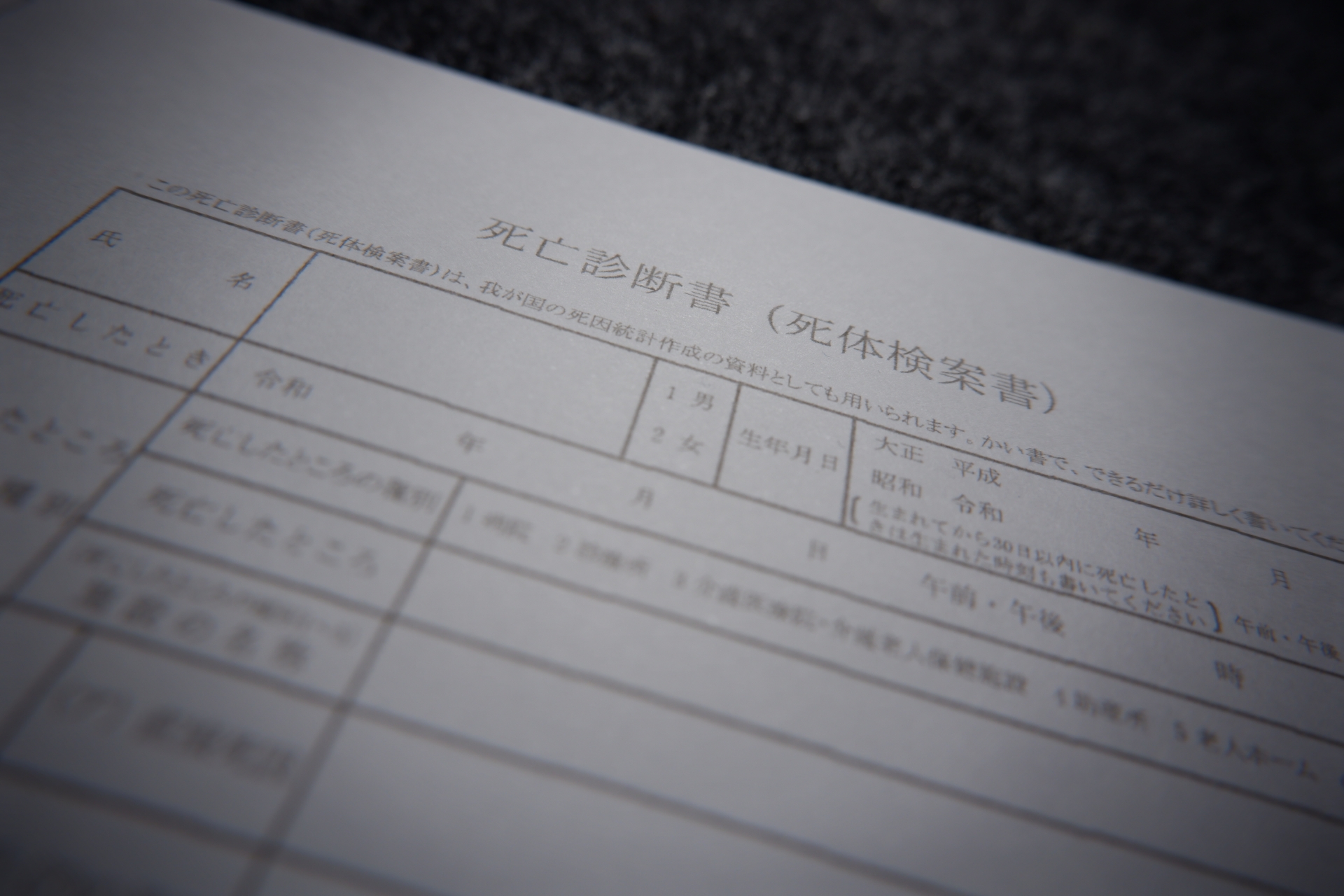
死因には、自殺や他殺、事故死や孤独死など大まかな分類を伝えることが求められます。ただし、遺族のプライバシーに配慮し、詳細な死因や背景事情まで説明する必要はありません。
自殺や他殺の場合は、事件の詳細ではなく死因のみを伝えます。孤独死の場合は、発見までの期間なども、買主の判断に影響があるため適切に告知をするとよいでしょう。
特殊清掃の有無
事故後に特殊清掃が行われたかどうかは、買主の判断に重要な影響を与える情報です。特殊清掃が行われた場合は、明確に伝える必要があります。
特殊清掃とは、通常の清掃では対応できない汚染や臭いを除去するための専門的な清掃のことです。血液や体液の除去、消臭・除菌処理、場合によっては床材や壁材の交換なども含まれます。
特殊清掃の実施は、事故の程度や物件への影響の大きさを示す指標です。そのため、特殊清掃実施の有無に関する告知は重要です。
情報が開示されなかった場合のリスク
告知義務を怠った場合、売主や不動産業者は重大な法的リスクを負うことになります。主なリスクには、以下のものがあります。
まず、損害賠償請求のリスクです。買主が事故物件であることを知らずに購入し、後からその事実を知った場合、精神的苦痛や財産的損害を理由とした損害賠償請求が予想されます。
次に、契約解除のリスクです。重要な情報が隠されていたことを理由に、買主が売買契約を解除する場合があります。この場合、売主は手付金や仲介手数料の返還などの経済的損失を被ることになります。
さらに、信用失墜のリスクも無視できません。関与した不動産業者も同様で、信用が損なわれ今後の取引に悪影響を及ぼす可能性があるでしょう。
事故物件の告知義務の対象になるケース

国土交通省が定めるガイドラインでは、告知義務の対象となる具体的なケースについて詳しく定められています。自分の物件がどのケースに該当するかを正しく把握することが、適切な対応の第一歩です。
自殺や他殺など事件性のある死亡の場合
自殺や他殺など、事件性のある死亡には、原則として告知義務の対象となります。これらの死亡は、一般の買主・借主の心理に大きな影響を与えるためです。
自殺の場合、その方法や場所に関わらず、室内で発生した場合は告知が必要です。ただし、ベランダや庭など、居住空間から離れた場所の場合は個別に告知判断を行います。
他殺の場合は、事件の規模や社会的な影響に関わらず、告知が必要です。特に、メディアで報道された事件には、長期間告知を求められることがあります。
事故死についても、その状況によっては告知が必要です。例えば、室内での転倒による死亡や入浴中の溺死なども個別に告知判断を行いましょう。
買主・借主からの確認があった場合

買主や借主から過去に事故はありましたか、人の死亡はありましたかといった質問があった場合は、たとえ告知義務の対象外であっても正直に答える必要があります。
これは、その情報が買主・借主の判断に影響を与える可能性が高いことを示しているためです。質問に対して虚偽の回答をしたり、回答を避けたりすることは信義則に反する行為とみなされます。
自然死であっても、買主から質問があった場合はその旨を正直に伝える必要があります。ただし、この場合も、故人のプライバシーに配慮し必要最小限の情報にとどめることが適切です。
質問への回答は、可能な限り書面で行うのが望ましいでしょう。口頭での回答だけでは、後々聞いていない、説明が不十分だったといったトラブルの原因となる可能性があります。
社会的に影響があると判断される場合
事故の内容や規模によっては、通常の基準を超えて長期間の告知が必要になる場合があります。これは、社会的な影響の大きさを考慮した判断です。
全国的にニュースで報道された事件や、地域社会に大きな衝撃を与えた事故は、何年経過しても多くの方の記憶に残るものです。
このような場合は、通常の期間を超えても告知が必要になります。また、インターネット上で事故の情報が検索可能な状態にある場合も、社会的影響があると判断されます。
そして、地域での認知度も重要な判断要素です。近隣住民の多くが事故のことを知っている場合、新しい住民がその情報を知る可能性が高いため、告知が必要になるでしょう。
成仏不動産なら、相続診断士の資格を持つスタッフが、告知義務の有無から適正価格の査定まで徹底的にサポートします。
さらに、特殊清掃やご供養、相続手続きまでワンストップで解決できる体制が整っているのも大きな強みです。
「すぐに現金化したい」という方には、最短即日での買取も可能です。複雑な告知義務の判断から売却まで、丸ごとお任せください。
まずはお気軽にご相談ください。あなたの物件の本当の価値を確かめてみましょう。
事故物件の告知義務が不要なケース

すべての死亡が告知義務の対象となるわけではありません。ガイドラインでは、原則として告知義務が不要とされるケースも明確に定められています。
老衰や病死など自然死の場合
老衰や病気による自然死には、原則として告知義務はありません。これらの死亡は、人生の自然な終わりであり、一般の買主・借主の判断に与える影響は低いと考えられるためです。
ただし、自然死であっても、次の場合は告知が必要になります。死亡の発見が大幅に遅れ、特殊清掃が必要になったような場合です。
これは、腐敗による汚染や臭いが物件に影響を与えているためです。また、自然死であっても、買主からの質問には正直に答える必要があります。
不慮の事故による死亡の場合

不慮の事故による死亡にも、状況によっては告知が必要です。一般的に日常生活のなかで起こる軽微な事故には、告知義務はないとされています。
階段での転倒や入浴中の軽微な事故などは、心理的影響は低いと考えられます。ただし、事故の状況や程度によっては告知が必要です。
重要なのは、事故の内容が買主の判断に影響を与える可能性があるかどうかです。一般の方がこの物件は避けたいと感じるような事故であれば、告知が必要と判断される可能性があります。
共用部分や敷地外での死亡の場合
共用部分である廊下や階段、エレベーターや敷地外での死亡には、原則として告知義務はありません。これは、居住空間ではないため、買主・借主の心理的負担が軽いと考えられるためです。
マンションの場合、共用部分での死亡は、特定の住戸の価値に直接的な影響はないとされています。ただし、エントランスや住戸の前など、日常的に利用する場所での死亡には個別の判断が必要です。
また、敷地外での死亡も同様で、原則として告知義務の対象外とされています。ただし、物件の前での事故など、物件との関連性が高い場合は告知が必要とされるでしょう。
買主からの質問には正直に答える必要があることは変わりません。また、事故の内容や社会的な影響によっては、例外的に告知が必要になることもあります。
特殊なケース

事故物件の告知義務はガイドラインで明確に定められていますが、一方で、判断が分かれる特殊なケースも存在します。
これらのケースでは、個別の状況を慎重に検討し専門家の意見を求めることが重要です。
自然死でも特殊清掃が必要な場合
原則として、老衰や病気による自然死は告知義務の対象外です。しかし、自然死であっても特殊清掃が必要になった場合は、告知義務が発生します。
特殊清掃が必要なケースでは、次のような状況が挙げられます。発見が遅れて腐敗が進み、通常の清掃では対応できない汚染や臭いが生じた場合です。
たとえ自然死であっても、長期間放置されたことで体液が床材に浸透したり、強い臭いが残ったりした場合は買主の判断に影響を与えると考えられます。
孤独死の場合も同様です。一人暮らしの高齢者が自然死し、数日から数週間発見されなかった場合、季節や室内環境によっては特殊清掃が必要になることがあります。
特殊清掃が行われた場合の告知内容は、自然死があったこと、特殊清掃を実施したことの両方を伝える必要があります。
ただし、故人のプライバシーに配慮し詳細な死因や個人情報は伝える必要はありません。
事故物件により大規模なリフォームが行われた場合
事故後に大規模なリフォームが行われた場合の告知義務も、判断が分かれるケースがあります。リフォームの実施は告知義務を免除するものではありません。
たとえ室内を完全に改装し、新築同様の状態にしたとしても、過去に事故があった事実は変わらないためです。ただし、リフォームの内容や程度は、告知の際に併せて伝えることが適切です。
例えば、〇年〇月に事故が発生し、その後に床材・壁材の全面張り替えや設備の交換などの大規模リフォームを実施済みとの情報提供で、買主がより適切な判断を下せるようになります。
特に、血液や体液による汚染があった部分を交換した場合は、その旨を明確に伝えることが重要です。物理的な汚染の除去を知ることで、買主の不安は軽減されるでしょう。
また、リフォームの時期も考慮する要素です。事故直後にリフォームを行った場合と、数年経過後にリフォームを行った場合では、買主が受ける印象は異なります。
告知義務違反によって生じるトラブル

告知義務を怠った場合、売主は深刻な法的リスクに直面することになります。実際の裁判例を踏まえ、具体的なトラブル内容を理解しておくことが重要です。
損害賠償の請求
告知義務違反の結果は、損害賠償請求です。買主が事故物件と知らずに購入し、その事実を後で知った場合、精神的苦痛や財産的損害を理由にした損害賠償請求が想定されます。
実際の裁判例では、前居住者の自殺を隠して賃貸契約を締結した事案で、賃貸人に対して損害賠償責任が認められました。
この事例では賃貸契約にかかる諸費用やエアコン工事代金、心理的ショックによる治療費や慰謝料、弁護士費用などが損害として認定されています。
売買の場合はさらに高額な損害賠償となるケースもあります。7年前に殺人事件が起きたことを隠して事故物件を売却した結果、売主に約2000万円もの損害賠償請求がなされた判例です。
損害賠償の範囲は、通常物件との価格差だけでなく、買主が物件購入のために要した諸費用や精神的苦痛に対する慰謝料まで広く認められる傾向にあります。
物件価格の減額請求

告知義務違反が発覚した場合、買主は物件価格の減額請求を行えます。
減額幅は、事故内容や物件への影響度によって決まります。一般的に、事故物件の相場は通常物件の1割から5割程度安く設定されているため、この差額分が減額請求額と考えるのが妥当です。
契約解除
告知義務違反は、契約解除の原因になります。重要な情報が隠されていたことで、買主が売買契約の解除を求めることは容易に想像できます。
契約解除が認められた場合、売主は、買主に対して次の費用の返金が必要です。物件購入時の手付金や売買代金、仲介手数料など買主が支払った費用全般が返金の対象です。
さらに、売主には契約解除により再度事故物件の売却活動を行う必要が生じ、その間の維持費用や機会損失も発生します。
履行追完請求
民法の契約不適合責任に基づき、買主は売主に対して履行追完請求ができます。これは、契約に適合した状態での履行を求める請求です。
事故物件の場合、事故がなかった物件を提供することは物理的に不可能なため、実際には代金減額請求や損害賠償請求が多くなります。
特殊清掃やリフォームが不十分だった場合には、追加の清掃・改修工事が要求されます。この場合、売主の負担でより徹底した対処が必要です。
事故物件の告知を行う際の注意点

適切な告知で、後々のトラブルを防ぐことができます。告知の方法や内容について、具体的な注意点を理解しておくことが重要です。
口頭だけなく書面で報告する
告知は書面で行うことが重要です。口頭での説明だけでは、後々聞いていない、説明が不十分だったといったトラブルの原因となることがあります。
書面での告知には、次の内容を明記することが必要です。まず、事故の発生時期については、〇年〇月頃と記載します。買主が内容を判断できる情報を提供します。
次に、事故の発生場所は居室内や浴室内、玄関付近など具体的な場所の明記が必要です。死因は、自殺や他殺、事故死や孤独死など大まかな分類を記載します。
詳細な死因や背景事情まで記載する必要はありません。特殊清掃の実施状況も、実施した場合はその旨を明記し、実施していない場合もその旨を記載します。
個人や遺族への配慮を忘れない

告知を行う際は、故人や遺族のプライバシーに十分な配慮が必要です。過剰な情報提供は、人権侵害にあたるおそれがあります。
氏名や住所などの個人情報は、告知の対象外です。買主に必要な情報は、事故の事実と基本的な状況であり、個人を特定できる情報は不要です。
遺族の心情に配慮し、必要以上に事故を強調したり、センセーショナルな表現をしたりすることは避けましょう。事実を淡々と伝える姿勢が重要です。
買主や借主が納得できる取引を心がける
告知の目的は、買主が十分な情報に基づいて適切な判断を下せることです。単に法的義務を果たすだけでなく、買主の立場に立った丁寧な対応が求められます。
質問には正直に答えることが基本です。買主から追加の質問があった場合は、知っている範囲で正確な情報を提供する必要があります。
曖昧な回答や回答の回避は、かえって不信を招く結果となります。リフォームや清掃の状況についても、積極的な情報提供が望ましいでしょう。
価格設定の根拠についても、説明できるよう準備しておくことが重要です。事故物件であることを踏まえた適正な価格設定を行い、その根拠を買主に説明できるようにしておきましょう。
成仏不動産は、事故物件買取の専門家です。
相続診断士の資格を持つスタッフが、価格設定、特殊清掃や遺品整理まで、ワンストップで対応します。さらに、司法書士や税理士とも連携しているため、相続や税務などの複雑な手続きもまとめて解決可能です。
「事故物件だから売れない」と諦める必要はありません。成仏不動産なら、全国どこでも最短即日現金化も可能です。事故物件の価値を正しく見極め、スムーズな売却をお手伝いします。
まずはお気軽にご相談ください。
事故物件の売却までの基本的な流れ

第1段階は、物件調査と現状把握です。まず、事故の詳細な記録を整理し、告知すべき内容を明確にします。事故の発生時期や場所、死因や特殊清掃の実施状況の正確な把握が重要です。
同時に、物件状態の詳細な調査も必要です。事故による物理的な影響が残っていないか、臭いや汚れの問題はないかを確認し、必要に応じて専門業者による調査を依頼します。
第2段階は、査定と価格設定です。査定と価格設定は、事故物件に精通した不動産業者に査定を依頼します。その際は事故物件の取り扱いが豊富な業者を選ぶことが重要です。
査定は、事故の内容や発生からの経過年数、物件の状態や立地条件などを総合的に考慮した適正な価格の設定です。
第3段階は、媒介契約と告知内容の整理です。この段階で選定した不動産業者と媒介契約を締結します。その際、告知すべき内容を業者と共有し、適切な告知方法について相談します。
告知書の作成も重要な作業です。前述の注意点を踏まえ、必要な情報を過不足なく記載した告知書を準備します。
第4段階は、販売活動です。事故物件であることを適切に告知しながら買主を探します。インターネット広告や不動産情報サイトへの掲載時でも、告知は必要です。
内覧時には、買主に対して直接告知を行い、質問があれば正直に答えましょう。この段階で十分な説明を行うことで、後々のトラブルを防ぐことができます。
第5段階は、契約締結です。売買契約書に告知内容を明記し、買主の理解と同意をえたうえで契約を締結します。重要事項説明書にも必要な情報を記載し、買主が十分に理解した状態で契約に進むことが重要です。
第6段階は、引渡しです。契約内容にしたがって物件を引き渡します。引渡し後に新たな問題が発生しないよう、事前確認の徹底が重要です。
事故物件の売却は、告知義務の判断や適正な価格設定、相続や税務の対応まで、専門知識が求められるとても複雑な手続きです。
成仏不動産は、事故物件の売却を知り尽くしたプロがお客様を徹底的にサポートいたします。
相続診断士の資格を保有したスタッフが、特殊清掃・供養・相続手続きまで、ワンストップで対応いたします。
「他社で断られた物件」や「告知義務がいつまでか分からない」といったお悩みも、私たちなら解決可能です。まずはお気軽にご相談ください。
事故物件の売却における相場

事故物件の売却相場を理解することは、適切な価格設定と現実的な期待値の設定に不可欠です。相場は事故の内容や物件の状況によって大きく異なります。
一般的な相場の目安として、事故物件の売却価格は通常物件の1割から5割程度安くなるとされています。具体的には自然死の場合は1割から2割、自殺の場合は2割から3割、殺人などの事件の場合は3割から5割程度の減額が一般的です。
ただし、これらの数値はあくまで目安であり、実際の価格はさまざまな要因によって変動します。立地条件が良好な物件では、事故物件であっても相対的に高い価格での売却が可能になります。
築年数や物件の状態も重要な要因です。新築に近い物件や設備が充実した物件では、事故による価格への影響が小さくなる傾向があります。
事故からの経過年数も価格に影響するのが一般的です。事故から長期間が経過している場合、心理的な影響が薄れ、価格への影響も小さくなります。
地域の特性も考慮すべき要素です。都市部では事故物件に対する抵抗感が小さく、地方では大きい傾向があります。また、賃貸需要が高い地域では投資用物件として購入する買主もいるため、価格への影響が限定的です。
リフォームや清掃の実施状況も価格に大きく影響します。事故後に適切な清掃やリフォームが行われている場合、買主の心理的負担が軽減され、価格への影響も小さくなります。
実際の相場を把握するためには、複数の不動産業者による査定を受けることが重要です。特に、事故物件の取り扱いが豊富な業者の意見は参考になります。
事故物件の相場でお悩みではありませんか?
成仏不動産なら、6,200件以上の相談実績をもとに、物件の状況や周辺市場データを踏まえた適正価格の査定が可能です。
相続診断士の資格を持ったスタッフが、単なる査定だけでなく、告知義務の判断や相続のご相談までワンストップでサポートします。
まずは無料査定で、実際の売却価格を確認してみませんか?事故物件の不安や疑問は、ぜひ以下からお気軽にご相談ください。
事故物件売却時に検討できる対処法

事故物件の売却を成功させるためには、物件の状況や市場環境に応じた適切な対処法の選択が重要です。複数の選択肢を検討し、適切な方法を選びましょう。
リフォームや清掃によって物件の印象を改善する
物件の印象改善は、事故物件売却の有効な手段の一つです。適切なリフォームや清掃により、買主の心理的負担を軽減し、売却価格の向上や売却期間の短縮を図ることができます。
特殊清掃の実施は、事故による汚染や臭いがある場合、不可欠です。通常の清掃では除去できない血液や体液の汚染、強い臭いなどは専門業者による特殊清掃で対応する必要があります。
また、内装リフォームも効果的な対処法です。壁紙の張り替えや床材の交換、設備の更新などにより、事故の痕跡を物理的に除去し買主に清潔で安全性の高い印象を与えることができます。
事故物件の買取業者に相談する
専門の買取業者への相談は、事故物件売却の現実的な選択肢です。一般の個人買主では敬遠されがちな事故物件でも、専門業者であれば積極的に買取を行っています。
買取のメリットとして、まず売却の確実性です。一般市場での売却では買主が見つからないことがありますが、買取業者であればすぐに売却できます。
売却期間の短縮も大きなメリットです。一般的な仲介売却では数ヶ月から1年以上かかる場合がありますが、買取業者であれば数週間から1ヶ月程度で売却が完了します。
手続きの簡素化も魅力です。買取業者は事故物件の取り扱いに慣れているため、告知義務への対応や必要書類の準備などをスムーズに進めることができます。
買取業者の選定では、事故物件の取り扱いが豊富な業者を選ぶことが重要です。経験豊富な業者であれば、適正な価格での買取が期待できます。
複数の業者から査定を取り、価格だけでなく対応の質も比較検討が大切です。事故物件の特性を理解し、適切な対応ができる業者を選びましょう。
「事故物件だから売れない」と諦めていませんか?
成仏不動産なら、どんな物件も前向きに買取検討いたします。
特殊清掃・ご供養・相続手続き・税務相談まで、司法書士・税理士・葬儀社・医療機関とのネットワークを活かして、すべてワンストップで対応可能です。複雑な手続きや余計なコストも抑えながら、最短即日で現金化を実現します。
さらに、相続診断士の資格を保有しているスタッフが、告知義務や相続放棄の判断など、専門的な悩みにも的確にお応えします。
「どこに相談すればいいかわからない」と迷っている方は、まずはお気軽にご相談ください。
事故物件の告知義務を正しく理解したうえで物件の売却を進めよう

事故物件の売却は、たしかに通常の不動産売却よりも複雑で困難な面があります。しかし、適切な知識と正しい対応により、トラブルを避けながら売却を成功させることは十分可能です。
告知義務の正しい理解が、売却成功の第一歩です。国土交通省のガイドラインに基づき、告知が必要なケースと不要なケースを正確に把握し、適切な対応を行うことで法的リスクを回避できます。
そして、誠実な情報開示こそが、長期的な成功につながります。事故の事実を隠したり、曖昧にしたりすることは、大きなトラブルの原因です。
専門家のサポートを積極的に活用しましょう。事故物件の取り扱いに精通した不動産業者や弁護士、税理士などの専門家の助言をえることで、より安全性が高く効率的な売却が可能になります。
事故物件の売却は困難ですが不可能ではありません。適切な準備と正しい対応で、所有者の納得できる売却が実現できるでしょう。
事故物件の売却は、複雑な手続きや心理的な負担が大きいものです。
しかし、私たち成仏不動産なら、相続・特殊清掃・ご供養まで、すべてワンストップで解決可能です。
どんな訳あり物件でも、本来の価値を正しく見極めて適正に買取します。さらに相続診断士の資格を保有しているスタッフが、告知義務や税務面の不安にも的確に対応します。
迷っている今こそ、解決の第一歩を踏み出すときです。
まずは成仏不動産の無料相談をご利用ください。あなたの事故物件に適切な解決策をご提案します。