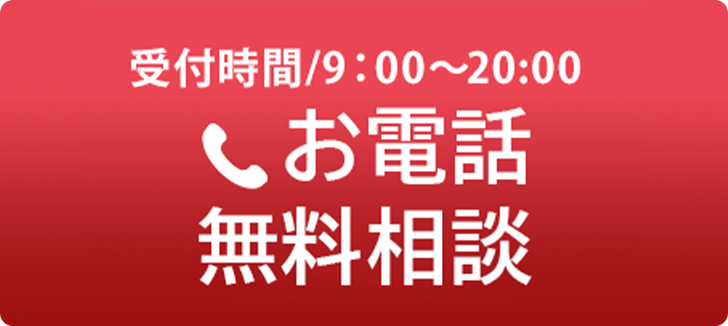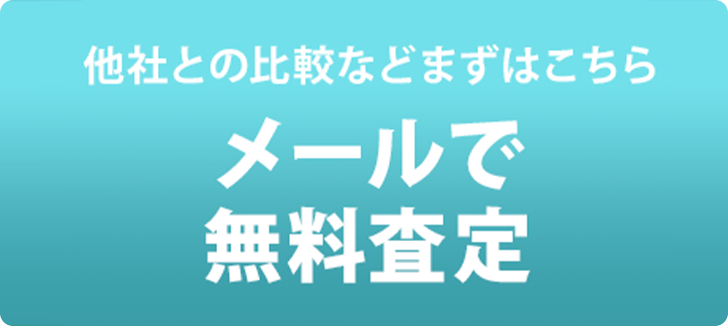飛び降りがあったマンションは事故物件か|告知義務の有無や売却相場への影響、売却方法も解説
2025年10月8日

所有するマンションで飛び降り事故が発生してしまった場合、多くの方が不安を抱えることでしょう。
これは事故物件になってしまうのだろうか、売却する際に買主に伝える必要があるのか、そもそも売却できるのかといった疑問が生じるはずです。
実は、飛び降りがあったからといって、すべてのケースが事故物件に該当するわけではありません。
本記事では、飛び降りがあったマンションが事故物件に該当する基準について詳しく解説していきます。
告知義務の有無、そして売却への影響についても、国土交通省のガイドラインに基づいて説明します。
適切な対応方法を理解することで、不安を解消し、前向きな判断ができるようになるはずです。
飛び降りがあったマンションは事故物件に該当するのか

飛び降りがあったマンションが事故物件として扱われるかどうかは、一律に決まるものではありません。
重要なのは、飛び降りが起きた場所や発生の性質によって判断が変わるということです。
例えば、自室のベランダから飛び降りがあった場合があります。一方で、マンションとは無関係の通行人が屋上から飛び降りた場合もあるでしょう。
これらのケースでは、心理的な影響の度合いが大きく異なります。また、自殺による飛び降りなのか、事故による転落なのかといった死因の違いも重要です。
これらの要素が、事故物件としての判断に影響を与えます。
国土交通省が2021年に発表した、宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドラインがあります。
このガイドラインでは、判断基準が明確化されており、ケースバイケースで慎重に検討する必要があることが示されています。
飛び降りがあったマンションが事故物件になるケース

飛び降りがあったマンションが事故物件として扱われる可能性が高いケースについて、具体的に見ていきましょう。
対象住戸からの飛び降り
売却を検討している住戸そのものから飛び降りがあった場合は、原則として事故物件に該当します。
これは、その部屋で生活することを想定する買主や借主にとって、心理的な負担が大きいと考えられるためです。
ガイドラインでは、他殺、自殺、事故死その他原因が明らかでない死亡が発生した場合について言及しています。
これらは買主・借主の判断に重要な影響を及ぼす可能性があるとされています。
したがって、対象住戸のベランダや窓から飛び降りがあった場合は、これを告知する必要があります。
対象住戸から飛び降りがあった場合の判断は特に慎重さが求められます。
このような状況でお悩みの方は、成仏不動産の専門スタッフが個別の事情に応じて丁寧にサポートいたします。まずは無料相談で、あなたの状況をお聞かせください。
隣接住戸や上下階からの飛び降り
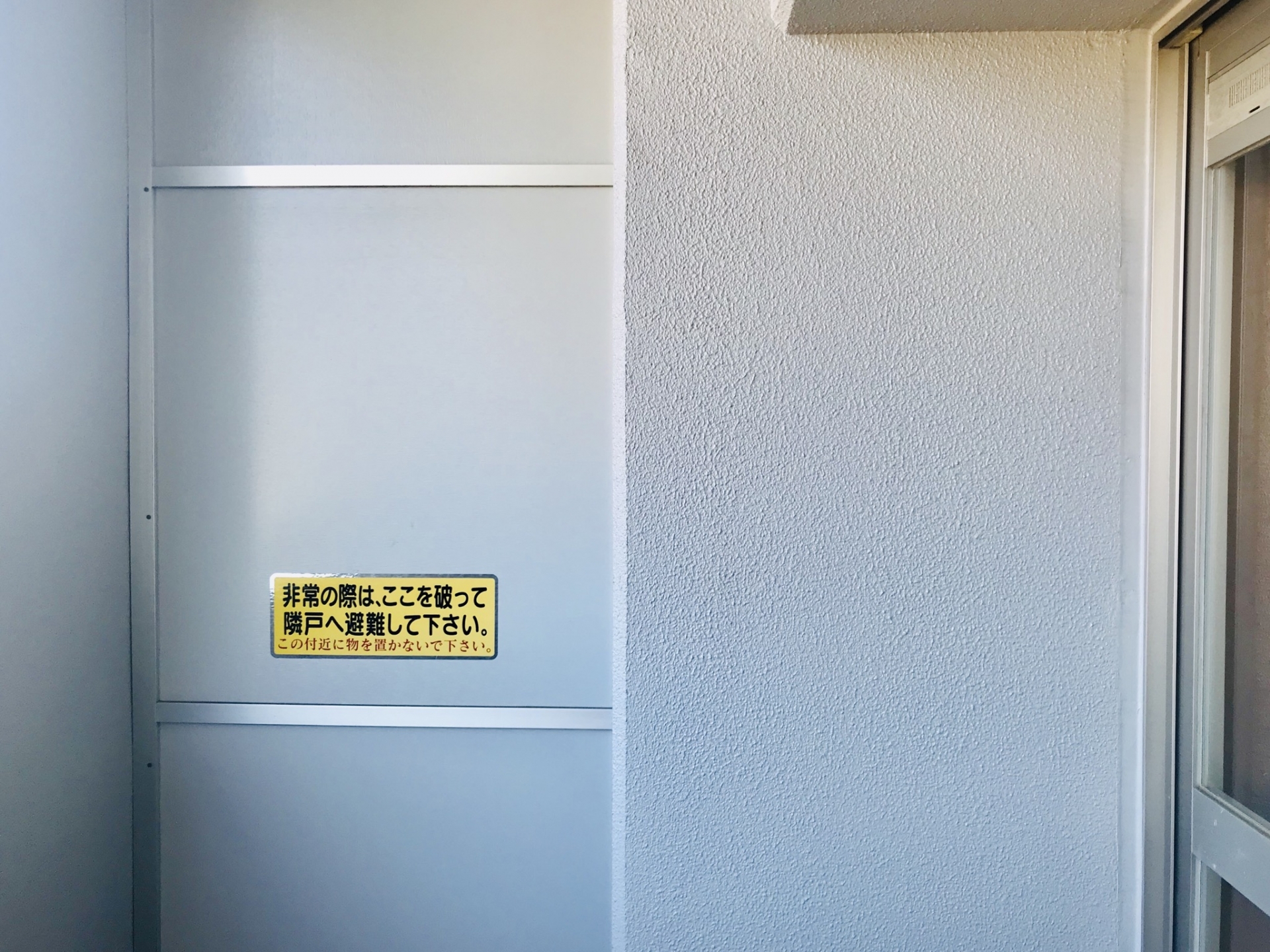
隣接する住戸や上下階から飛び降りがあった場合の扱いは、やや複雑です。
ガイドラインによれば、賃貸借取引および売買取引において、隣接住戸で他殺、自殺、事故死が発生した場合があります。
この場合は、原則として告知不要とされています。
ただし、事件性、周知性、社会に与えた影響などが特に高い事案については、この限りではありません。
例えば、大きく報道されて周知の事実となっている場合や、複数の住戸に心理的影響を与えるような状況であった場合です。
このような場合は、告知を検討する必要があるでしょう。
自殺や他殺など事件性のある飛び降り

飛び降りの原因が自殺や他殺である場合、これは明確に事故物件として扱われます。
ガイドラインにおいて、他殺、自殺については、買主・借主の判断に重要な影響を及ぼす可能性があるものです。
これらは原則的に告知すべき事案として位置づけられています。
一方で、階段からの転落など、日常生活のなかで生じた不慮の事故による死については異なります。
そのような死が生ずることは当然に予想されるものであり、原則として告知の必要はないとされています。
ただし、長期間にわたって人知れず放置され、特殊清掃などが行われた場合は例外となります。
心理的瑕疵が残る期間内の飛び降り
事故物件としての心理的瑕疵がいつまで続くかという点も重要です。
賃貸借取引については、ガイドラインで明確な基準が示されています。
おおむね3年間を経過した後は、原則として、借主に対してこれを告げなくてもよいとされています。
しかし、売買取引については明確な期間の定めはありません。
事案の内容や社会的影響を考慮して個別に判断する必要があるでしょう。
特に事件性が高い場合や、広く知られている事案については注意が必要です。
3年を経過しても告知が必要となる可能性があります。
飛び降りがあっても事故物件に該当しにくいケース

すべての飛び降りが事故物件として扱われるわけではありません。
部外者による飛び降りの場合、マンションの住人ではない第三者が関わったケースです。
たまたまそのマンションを選んで飛び降りた場合、物件そのものとの関連性が薄いため、心理的瑕疵が発生しにくいと考えられます。
また、物件とは無関係な場所での飛び降りも、原則として告知義務の対象外となります。
例えば、マンションの前の道路や、敷地外での飛び降りは該当しません。
ガイドラインでも基本的に告知の必要がないとされています。
ただし、これらのケースでも、事件の規模や社会的影響が大きい場合は別です。
買主の判断に重要な影響を与える可能性がある場合は、告知を検討する必要があるでしょう。
判断に迷う場合は、専門家に相談することが賢明です。
共用部分からの飛び降りについて

マンションの共用部分での飛び降りは、個別の住戸とは異なる基準で判断されます。
全住民が利用する空間であるため、その影響範囲や告知義務の判断には特別な配慮が必要です。
共用部分で発生した飛び降りは事故物件に該当するか
ガイドラインによれば、借主もしくは買主が日常生活において通常使用しない集合住宅の共用部分について定めがあります。
これらで発生した事案については、原則として告知不要とされています。
例えば、普段使用しない屋上や機械室などがこれに該当します。
一方で、日常生活において通常使用する共用部分については、賃貸借取引の対象不動産と同様に扱うとされています。
これには、共用の玄関、エレベーター、廊下、階段のうち、日常的に使用する部分が含まれます。
共用部分での飛び降りによる資産価値への影響
共用部分での飛び降りが資産価値に与える影響は、発生場所や状況によって異なります。
エントランスや日常的に使用する階段での事案は、住民の心理的負担が大きくなります。
そのため、資産価値への影響も無視できません。
実際の取引では、共用部分での事案であっても、買主から質問された場合には誠実に答える必要があります。
ガイドラインでも、買主・借主から事案の有無について問われた場合の対応が定められています。この場合には、判明している事実を告げる必要があるとしています。
共用部分の利用頻度による告知義務の有無
共用部分の利用頻度は、告知義務の判断において重要な要素となります。
毎日通る廊下やエレベーターと、年に数回しか使わない屋上では異なります。心理的影響の度合いが大きく異なるためです。
日常的に使用する共用部分での事案は、たとえ自室ではなくても影響があります。
居住の快適性に影響を与える可能性があるでしょう。
そのため、利用頻度が高い共用部分での飛び降りについては、告知を検討する必要があります。
共用部分での事案について判断に迷われている方も少なくないのではないでしょうか。
成仏不動産では、事故物件・遺品整理・特殊清掃まで総合的にサポートしており、複雑なケースにも対応可能です。
まずは無料相談で、適切な対処方法を一緒に考えましょう。
宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドラインとは
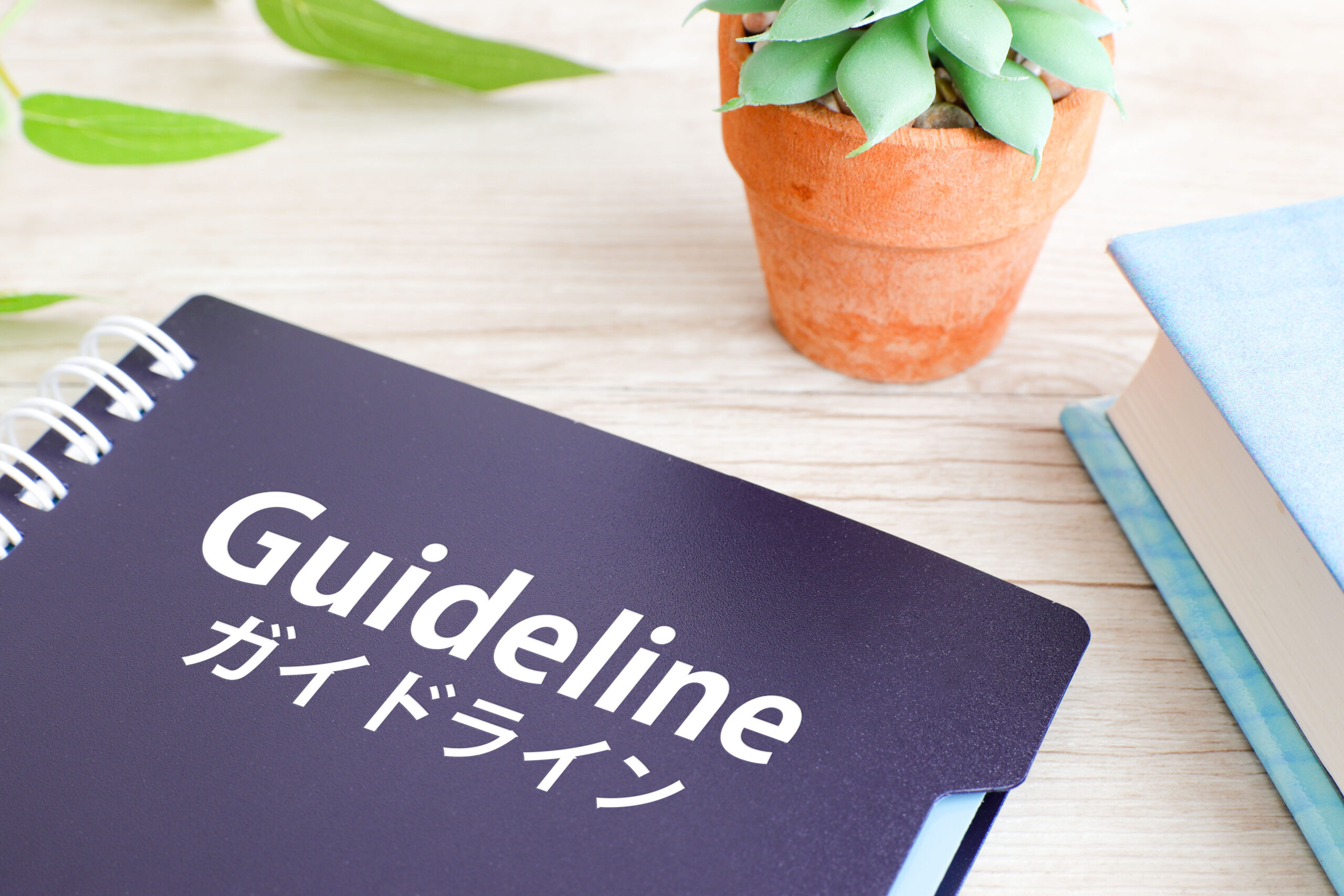
国土交通省が2021年10月に発表したガイドラインは、不動産取引における人の死の告知について統一的な基準を示しています。
これまで曖昧だった告知義務の範囲や期間が明確になりました。
ガイドライン発表の背景
このガイドラインが制定された背景には、不動産取引における深刻な課題がありました。
人の死に関する事案の告知について、宅地建物取引業者によって対応がまちまちだったことです。
なかには過度に慎重になるあまり、すべての死亡事案を告知するケースもありました。
このような状況は、特に高齢者の賃貸住宅への入居を困難にする要因ともなっていました。
貸主が、入居者が亡くなった場合の告知義務を恐れていたからです。
そのため単身高齢者の入居を敬遠する傾向もありました。
ガイドラインは、このような課題を解決するために制定されました。
適切な情報開示と円滑な不動産取引の両立を図ることが目的です。
現時点で妥当と考えられる一般的な基準を示すことで、トラブルの未然防止と不動産取引の適正化を目指しています。
告知を行うための調査内容
ガイドラインでは、宅地建物取引業者の調査義務について明確に定めています。
業者は、販売活動・媒介活動に伴って通常の情報収集を行う義務があります。
ただし、人の死に関する事案を疑わせる特段の事情がない限り、自発的に調査する義務まではないとされています。
具体的には、売り主・貸主に対して告知書(物件状況等報告書)への記載を求めることになります。
これにより、通常の調査義務を果たしたものとされます。
告知書に記載されなかった事案が後日判明しても、宅地建物取引業者に重大な過失がない限り、調査は適正に行われたものとみなされます。
調査範囲や告知書への記載方法でお困りの場合は、プロのアドバイスが役立ちます。
成仏不動産では、これまで多くの事故物件を取り扱ってきた実績があり、適切な調査・告知方法をご提案できます。
まずは無料相談で、不安を解消しませんか。
事故物件とは
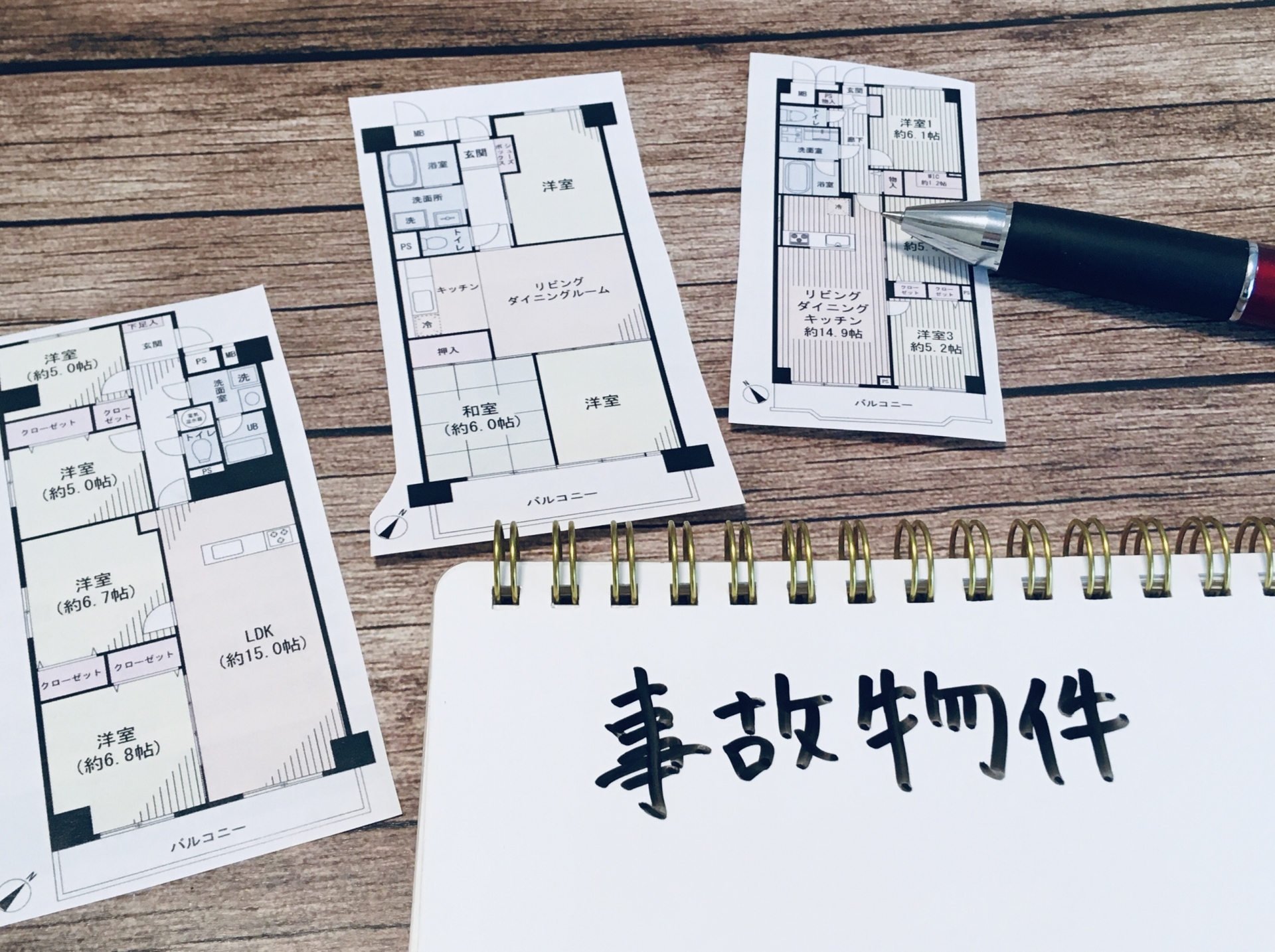
事故物件とは、過去に人の死が発生し、買主・借主の心理に影響を与える可能性がある物件を指します。
その具体的な定義について詳しく解説します。
入居者の死亡が発生した物件
事故物件の基本的な定義は、入居者の死亡が発生した物件です。
ただし、すべての死亡が事故物件につながるわけではありません。
老衰や持病による病死など、いわゆる自然死については、居住用不動産で発生することは当然に予想されるものです。
そのため、原則として告知の必要はないとされています。
実際、統計によれば、自宅における死因の約9割は老衰や病死による自然死です。
これらは一般的な出来事として扱われます。
買主・借主の判断に重要な影響を及ぼす可能性は低いと考えられています。
自殺・他殺など事件性のある物件
自殺や他殺など、事件性のある死亡が発生した物件は、明確に事故物件として扱われます。
これらの事案は、買主・借主の心理に大きな影響を与えるからです。
契約締結の判断を左右する可能性が高いためです。
ガイドラインでも、他殺、自殺、事故死その他原因が明らかでない死亡が発生した場合について定めています。
これらは原則として告知すべき事案として位置づけられています。
心理的瑕疵がともなう物件
心理的瑕疵とは、物理的な欠陥はないものの、通常一般人が心理的に嫌悪感を抱くような事情がある状態を指します。
人の死以外にも、過去の使用用途や周辺環境なども心理的瑕疵の原因となることがあります。
心理的瑕疵の判断は主観的な要素が強く、個人差があることも事実です。
しかし、不動産取引においては、一般的な感覚として重要な影響を与える可能性がある事項について対応が必要です。
適切に告知することが求められています。
事故物件における告知義務とは

事故物件における告知義務は、不動産取引の公正性を保つための重要な制度です。
売り主や宅地建物取引業者は、買主・借主が適切な判断を下せるよう、必要な情報を提供する義務があります。
宅地建物取引業法では、取引条件に関する重要事項について定めがあります。
相手方の判断に重要な影響を及ぼすこととなるものについて、故意に事実を告げない行為が禁じられています。
また、不実のことを告げる行為も禁止されており、違反した場合は業務停止処分などの行政処分の対象となる可能性があります。
民事上の責任も発生します。告知義務違反により買主が損害を被った場合、損害賠償請求の対象となることがあります。
そのため、疑わしい場合は告知する、といった慎重な姿勢が重要となります。
ガイドラインに基づく告知義務の期間

告知義務がいつまで続くかという問題は、実務上大変重要です。
賃貸借取引については、おおむね3年間という具体的な期間が示されています。
他殺、自殺、事故死が発生してからおおむね3年を経過した後は、原則として告知の必要はないとされています。
一方、売買取引については、明確な期間の定めはありません。
これは、売買取引が賃貸借取引に比べて取引金額が高額であるためです。
トラブルが生じた場合の損害も大きくなりやすいという事情があります。
事案の内容、発生からの経過時間、社会的影響などを総合的に考慮して、個別に判断する必要があるでしょう。
ただし、いずれの場合も、事件性、周知性、社会に与えた影響などが特に高い事案については注意が必要です。
これらの期間に関わる告知が必要となることがあります。
事故物件の告知義務内容

告知では、ガイドラインで示された3つの要素を適切に伝える必要があります。
過不足のない情報提供により、トラブル防止とプライバシー保護の両立が可能です。
発生時期
事案の発生時期は、告知すべき重要な情報の一つです。
いつ頃の出来事なのかによって、買主・借主の受け止め方も変わってくるためです。
ただし、正確な日付まで特定できない場合は、〇年前頃といったかたちで伝えれば十分でしょう。
把握している範囲で情報提供することが大切です。
特殊清掃などが行われた場合は、死亡時期ではなく発覚時期を基準とすることも重要なポイントです。
発生場所
発生場所についても、具体的に伝える必要があります。
同じマンション内でも、自室内なのか、ベランダなのか、共用部分なのかによって異なるからです。
心理的影響の度合いが変わってくるためです。
ただし、あまりに詳細な情報まで伝える必要はありません。
買主・借主が判断するのに必要な程度の情報を提供すれば十分です。
死因
死因については、他殺、自殺、事故死などの区別を伝えることが求められています。
ただし、詳細な死亡原因や状況まで説明する必要はありません。
また、原因が明らかでない場合は、その旨を正直に伝えることが大切です。
亡くなった方やその遺族の名誉および生活の平穏に配慮する必要があります。
氏名、年齢、住所、家族構成などの個人情報は告げる必要はありません。
飛び降りがあったことを告知しなかったときに起こるトラブル

告知義務を怠ると、売り主は深刻な法的リスクに直面します。
後から事実が発覚した際のトラブルは、経済的にも精神的にも大きな負担となるでしょう。
損害賠償請求
一般的なトラブルは、買主からの損害賠償請求です。
購入後に飛び降りの事実を知った買主は、知っていれば購入しなかったと主張することがあります。
もっと安い価格で購入できたはずだとして、差額分の賠償を求めることもあるでしょう。
裁判例でも、告知義務違反による損害賠償責任を認めたケースは多数存在します。
賠償額は、物件価格の減価分や、精神的苦痛に対する慰謝料など、状況によってさまざまです。
数百万円から場合によっては1000万円を超える賠償が命じられることもあります。
減額請求
契約締結後、引渡し前に事実が判明した場合、買主から購入価格の減額請求を受けることがあります。
減額の幅は、事案の内容や物件の特性によって異なるでしょう。相場の2割から5割程度の減額を求められることも珍しくありません。
契約解除
深刻なケースとして契約解除があります。
買主が重要な事実を隠されていたとして、契約の解除を求めることがあります。
契約が解除されれば、売買代金の返還はもちろん、買主が支出した諸費用の賠償も必要になる可能性があるでしょう。
さらに、宅地建物取引業者が関与している場合、業法違反として行政処分の対象となることもあります。
このような深刻なトラブルを未然に防ぐためにも、売却前に専門家のアドバイスを受けることが大切です。
成仏不動産では、持ち出し0円で問題解決が可能な買取プランもご用意しています。
まずは無料相談で、リスクを抑える方法をご提案いたします。
飛び降りがあった場合の売買価格への影響

飛び降りがあったマンションは、発生場所や状況により価格への影響が異なると考えられます。
心理的瑕疵がある物件の取引においては、通常の相場より低い価格での取引となる可能性があります。
部屋からの飛び降りの場合
対象となる部屋から直接飛び降りがあった場合、売買価格への影響は大きくなると考えられます。
特に、事件が広く報道されたり、地域で知られている場合は、さらに影響を受ける可能性があります。
ただし、立地条件が良好で需要が高い地域では、影響が小さく済むこともあるでしょう。
また、時間の経過とともに影響は徐々に薄れていく傾向があると考えられます。
共用部からの飛び降りの場合

共用部分からの飛び降りの場合、価格への影響は相対的に小さくなる傾向があると考えられます。
ただし、エントランスや日常的に使用する階段など、避けて通れない場所での事案は、より大きな影響を与える可能性があります。
価格設定にお悩みの方は、一人で抱え込まず専門家にご相談ください。
成仏不動産では、事故物件でも適正価格での買取が可能です。
諸費用や売却にかかる費用も持ち出し0円で対応できるケースもあります。まずは無料相談で、適切な売却方法を見つけましょう。
飛び降りがあったマンション売買の流れ

飛び降りがあったマンションでも、適切な手順で売却は可能です。事故物件特有の配慮点を踏まえた売却の流れを説明します。
売却査定を依頼する

まず、複数の不動産会社に査定を依頼します。
この際、飛び降りの事実を正直に伝えることが重要です。
事故物件の取り扱い経験がある業者を選ぶことで、より適切な査定と販売戦略の提案を受けることができるでしょう。
媒介契約を結ぶ
査定結果を踏まえて、信頼できる不動産会社と媒介契約を結びます。
事故物件の販売には特別な配慮が必要なため、経験豊富な担当者がいる会社を選ぶことが成功の鍵となるでしょう。
販売活動と内見対応
販売活動では、事故物件であることを適切に開示しながら、物件の魅力も同時にアピールしていきます。
立地の良さ、設備の充実度、管理状態の良さなど、ポジティブな要素も積極的に伝えることが重要です。
内見対応では、質問に対して誠実に答える姿勢が大切です。
事実を隠したり、曖昧にしたりすることは、後のトラブルの原因となります。
契約・引き渡し
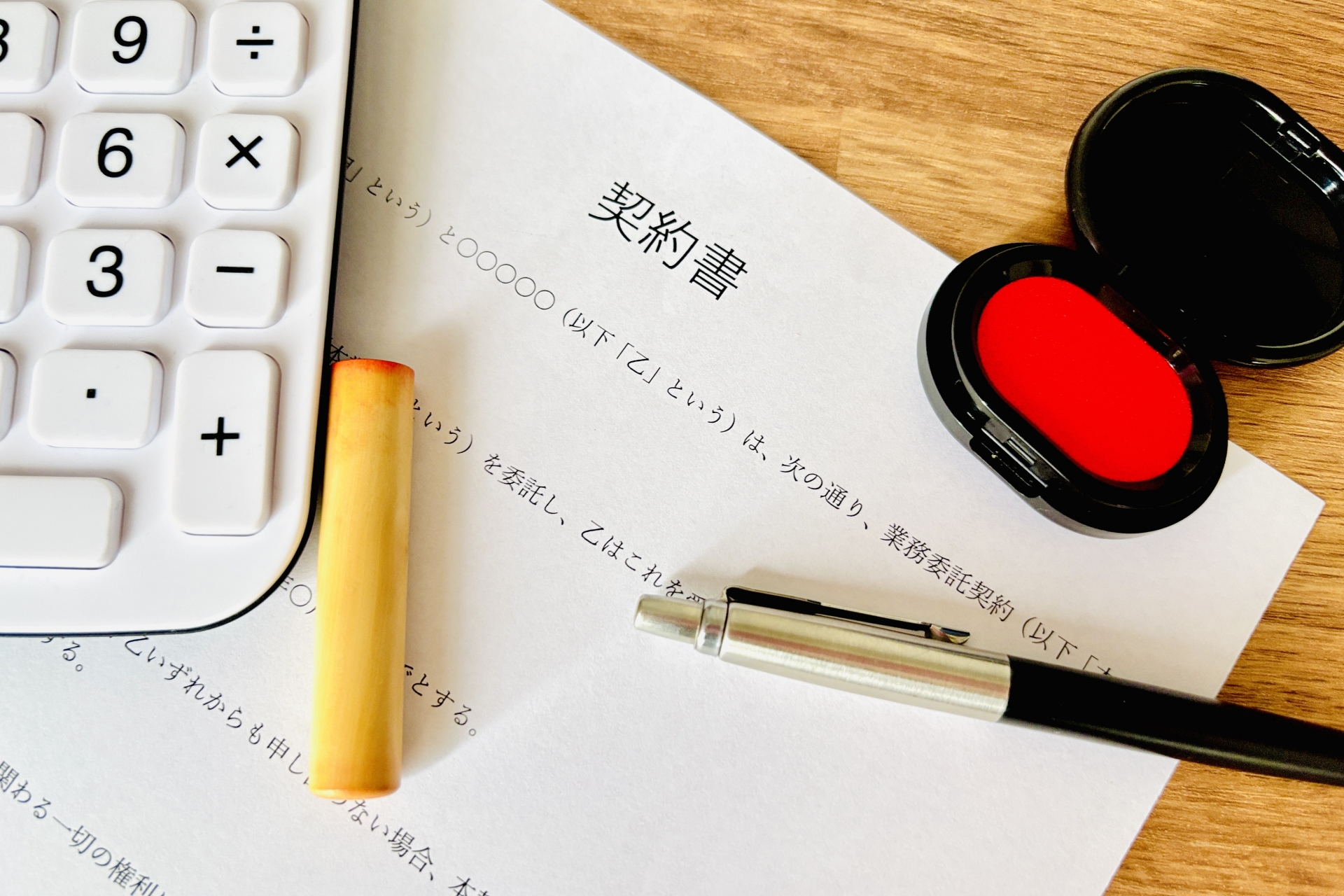
買主が見つかったら、重要事項説明書に飛び降りの事実を明記したうえで、売買契約を締結します。
この際、買主が事実を認識したうえで購入することを書面で確認することが重要です。これが後のトラブル防止につながります。
飛び降りがあったマンションが売れないときの対処法

通常の販売で売れない場合も、さまざまな対処法があります。
状況に応じた選択肢を検討することで、売却の可能性を高められるでしょう。
値下げで成約率を高める

直接的な対処法は、価格の見直しです。市場の反応を見ながら段階的に価格を下げることで、購入検討者の層を広げることができます。
ただし、安易な値下げは損失を拡大させるだけなので、不動産会社と相談しながら戦略的に行うことが重要でしょう。
清掃・リフォーム・必要に応じて特殊清掃を行う
物件の印象を改善することも有効な対策です。
徹底的な清掃やリフォームにより、心理的な抵抗感を和らげることができます。
不動産会社に買取を依頼する
仲介での売却が困難な場合、不動産会社による直接買取も選択肢の一つです。
買取価格は市場価格より低くなりますが、売却が可能です。現金化までの期間も短いというメリットがあります。
事故物件専門の仲介業者や買取業者に相談する
近年では、事故物件を専門に扱う専門業者も増えています。これらの業者は、事故物件の取り扱いに関する豊富な経験とノウハウを持っています。
通常の不動産会社では対応が難しいケースでも、適切な解決策を提案してくれるでしょう。
飛び降りがあったマンションの売却は専門業者への相談しよう

ここまで、飛び降りがあったマンションの取り扱いについて詳しく解説してきました。
事故物件に該当するかどうかの判断、告知義務の内容と期間、売却への影響など、考慮すべき点は多岐にわたります。
重要なのは、これらの判断を一人で行うのは難しいということです。
法的な知識、不動産取引の経験、そして繊細な配慮が求められる事故物件の売却は、プロフェッショナルのサポートが不可欠です。
専門的な知識と経験を持つ業者の協力が必要となるでしょう。
事故物件に不慣れな不動産会社では、適切な対応ができないばかりか、かえってトラブルを招く可能性もあります。
一方、事故物件を専門に扱う業者であれば、法的リスクを回避しながら対応してくれます。
適切な売却方法を提案してくれるでしょう。
事故物件の売却でお困りの方は、ぜひ成仏不動産にご相談ください。365日受付で、全国どこでも対応可能です。
相続から売却まで、不動産に関する悩みを総合的にサポートし、持ち出し0円での問題解決も可能です。
「一人で悩まず相談してよかった」「話を聞いてもらえて安心した」というお客様の声を多数いただいています。まずは無料相談で、あなたの不安をお聞かせください。
飛び降りがあったという事実は変えることはできません。
しかし、適切な対応と誠実な姿勢があれば、解決の道は開けます。
一人で悩みを抱え込まず、専門家の力を借りながら、より良い解決策を見つけていきましょう。
事故物件の売却は、通常の不動産取引よりも複雑で、精神的な負担も大きいものです。
しかし、適切な知識と対応方法を理解し、信頼できる専門業者のサポートを受けることで前に進むことができます。
最後にあらためて強調したいのは、告知義務を適切に果たすことの重要性です。
事実を隠そうとすることは、後に大きなトラブルを招く原因となります。
誠実な対応こそが、売り主と買主の双方にとってより良い結果をもたらすでしょう。
飛び降りがあったマンションの売却を検討されている方は、まず専門業者に相談し、ご自身の状況に適切な解決策を見つけてください。
プロフェッショナルのサポートを受けることで、不安や疑問を解消し、新たな一歩を踏み出すことができるでしょう。適切な対応により、明るい未来が待っています。